
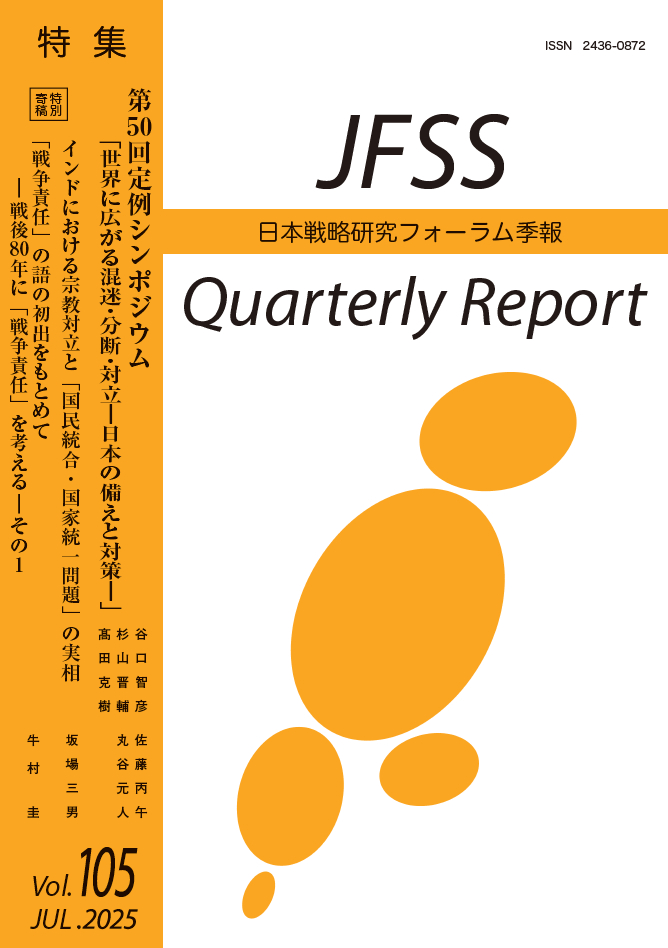
― 目次 ―
| 序文 | 福澤諭吉 人生の美学 ―諭吉と人生の間― |
渡辺利夫 |
| 巻頭言 | 「良民」による「良キ政府」を作るために―『学問のすゝめ』を再読して― | 丹羽文生 |
| 《基調講演》 | 世紀の分水嶺がいまそこに | 谷口智彦 |
| 《講 演》 | 今後の日本外交 | 杉山晋輔 |
| 《講 演》 | 日本の備えと対策 | 髙田克樹 |
| 《講 演》 | トランプ政権の目指す国際秩序とは何か? | 佐藤丙午 |
| 《講 演》 | 日本の危機意識に対する警鐘 | 丸谷元人 |
| 《オープンディスカッション》 | 杉山晋輔氏、髙田克樹氏、佐藤丙午氏、 丸谷元人氏によるディスカッション |
|
| <モデレーター>田北真樹子 | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| インドにおける宗教対立と「国民統合・国家統一問題」の実相 | 坂場三男 | |
|
牛村 圭 |
||
| ずれまくっている共産党志位議長 |
筆坂秀世 | |
| 尖閣問題、竹島と同じ轍を踏むことなかりしや―その4― | 向田昌幸 | |
| 英霊を祀る「靖國神社」から沖縄県祖国復帰53周年の「祝賀」を | 本松敬史 | |
| 【特別研究】 | ||
| 中国と北朝鮮、血盟と相克の歴史 | 藤谷昌敏 | |
| 1944年「流血の夏」における日本陸軍の諜報活動 | 増永真悟 | |
| 戦後の日英和解と重光葵 | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第17回 グレーゾーン事態への対処 |
武藤茂樹 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第189回~第190回報告 | 長野禮子 |
|
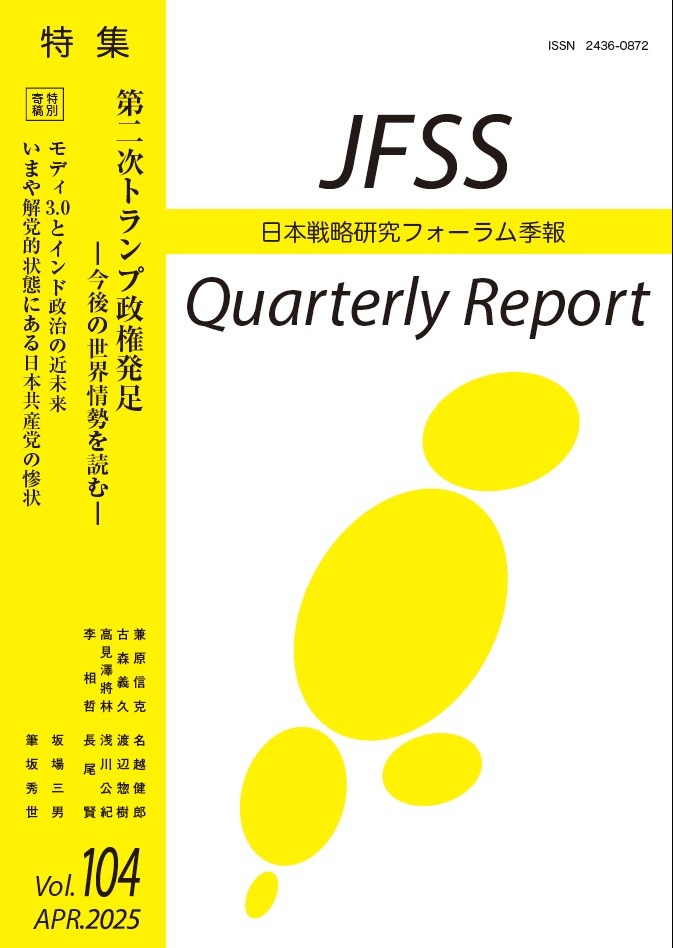
― 目次 ―
| 序文 | 陸奥宗光よ、再び。 |
渡辺利夫 |
| 巻頭言 | 高砂義勇隊の大和魂 ―日本人として従軍した台湾の原住民― |
丹羽文生 |
|
【特集】第二次トランプ政権発足 ―今後の世界情勢を読む― |
||
| トランプ2.0と日本 | 兼原信克 | |
| トランプ大統領就任後の世界情勢を読む | 古森義久 | |
| 第二次トランプ政権発足後の国際関係と日本の安全保障 | 髙見澤將林 | |
| トランプ政権で韓国・北朝鮮はどうなるのか | 李 相哲 | |
| ウクライナ戦争、「トランプ停戦」は実現するか | 名越健郎 | |
| 米国は司法の武器化を止められるか ―新FBI長官に期待する― |
渡辺惣樹 | |
| トランプ再登場で世界はどう変わるか | 浅川公紀 | |
| トランプ政権でQUADはどうなるか | 長尾 賢 |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| モディ3.0とインド政治の近未来 | 坂場三男 | |
| いまや解党的状態にある日本共産党の惨状 | 筆坂秀世 | |
| 尖閣問題、竹島と同じ轍を踏むことなかりしや ―その3― |
向田昌幸 |
|
| 【特別研究】 | ||
| 中国の国内外の治安維持活動を支援、拡大する民間警備会社 | 藤谷昌敏 | |
| 戦間期の日本・フィンランド軍事関係史―1930~1940年― | 増永真悟 | |
| 地政学とは何か―混迷の世界を生き抜くために― | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第16回 核問題に対する政治の覚悟 |
荒木淳一 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第186~188回報告 | 長野禮子 |
|
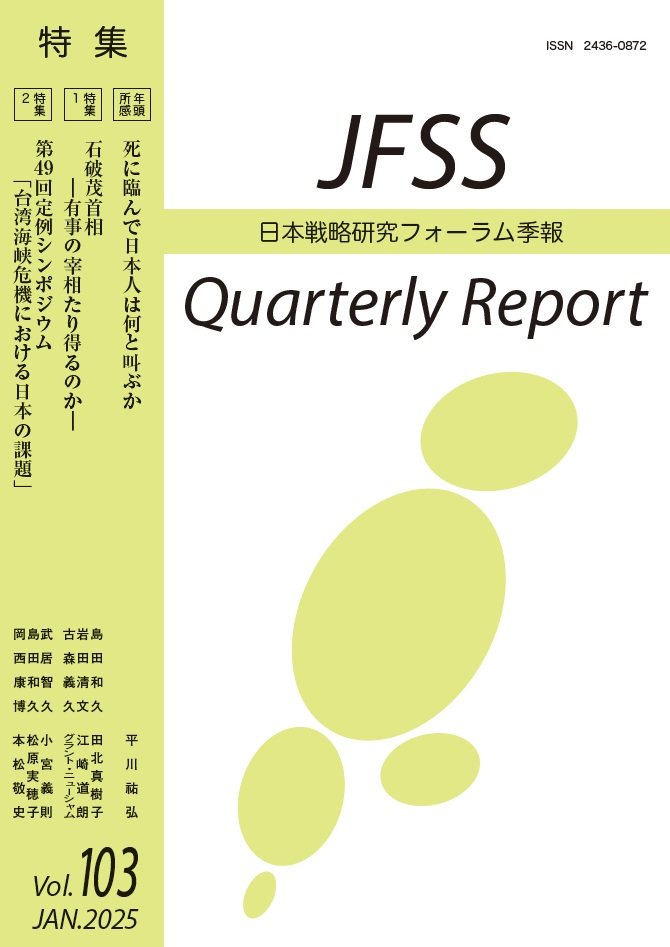
― 目次 ―
| 序文 | 会長就任に当たって ―大いなるナショナリスト福澤諭吉― |
渡辺利夫 |
| 年頭所感 | 死に臨んで日本人は何と叫ぶか | 平川祐弘 |
| 巻頭言 | 躍進の国民民主党「令和の民社党」を目指せ | 丹羽文生 |
|
【特集1】石破茂首相 ―有事の宰相たり得るのか― |
||
| 島田和久 | ||
| 岩田清文 | ||
| アメリカとの信頼関係をどう築くか | 古森義久 | |
| 理想主義者は「天命」をどう解釈するか | 田北真樹子 | |
| 「インテリジェンスの抜本的強化を期待する」 | 江崎道朗 | |
| トランプ氏を必要以上に恐れる必要はない 寧ろ日本の方が心配だ |
グラント F. ニューシャム |
|
【特集2】第49回定例シンポジウム「台湾海峡危機における日本の課題」 |
||
| 《講 演》 | 武居智久 | |
| 《オープンディスカッション》 |
島田和久氏、小宮義則氏、岡西康博氏、松原実穂子氏、本松敬史氏によるディスカッション
<モデレーター>田北真樹子 |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| 民族・宗教の多様性が阻む東南アジアの地域統合 | 坂場三男 | |
| なぜ日本共産党は選挙で大敗したのか | 筆坂秀世 | |
| 向田昌幸 | ||
| 【特別研究】 | ||
| 藤谷昌敏 | ||
| 「冬戦争」における日本陸軍のフィンランドでの諜報活動 | 増永真悟 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第15回 日本人の心情について ―「アジア版NATO」報道を聞いて感じたこと― |
湯浅秀樹 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第183~185回報告 | 長野禮子 | |
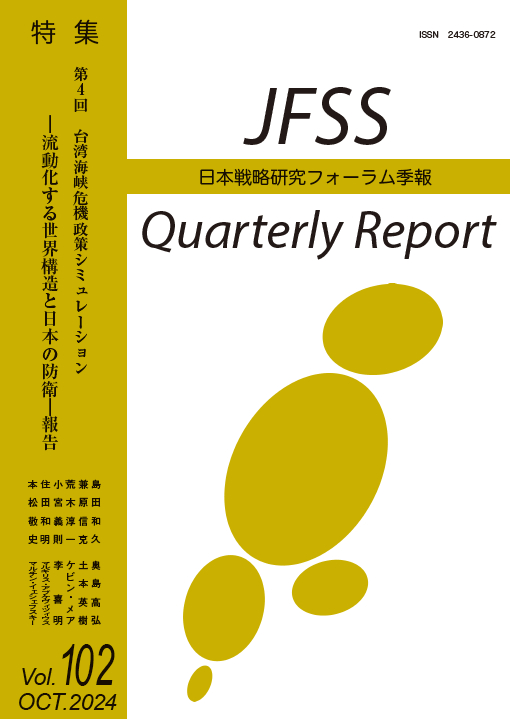
― 目次 ―
|
序文
|
渡辺利夫
|
|
|
巻頭言
|
丹羽文生
|
|
|
【特集】第4回台湾海峡危機政策シミュレーション ー流動化する世界構造と日本の防衛ー 報告
|
||
|
島田和久
|
||
|
兼原信克
|
||
|
荒木淳一
|
||
|
小宮義則
|
||
|
住田和明
|
||
|
本松敬史
|
||
|
奥島高弘
|
||
|
土本英樹
|
||
|
ケビン・メア
|
||
|
(Eng.)
|
Kevin K. Maher
|
|
|
李 喜明
|
||
|
(Eng.)
|
Lee Hsi-min
|
|
|
マルギリス・アブケヴィツィウス
|
||
|
(Eng.)
|
Margiris Abukevičius
|
|
|
マルチン・イェシェフスキー
|
||
|
(Eng.)
|
Marcin Jerzewski
|
|
|
【日台交流】
|
|
|
|
JFSS 事務局
|
||
| 【特別寄稿】 |
|
|
|
坂場三男
|
||
|
筆坂秀世
|
||
|
向田昌幸
|
||
| 【特別研究】 |
|
|
|
藤谷昌敏
|
||
|
橋本量則
|
||
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 |
|
|
|
山村 浩
|
||
| 【Key Note Chat 坂町】 |
|
|
|
長野禮子
|
||
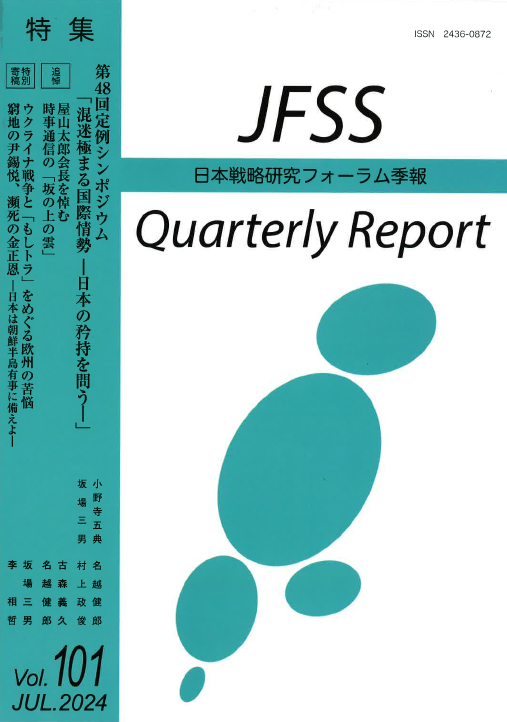
― 目次 ―
| 【追悼】 | 渡辺利夫 | |
| 兄貴と慕った人との別れ | 長野俊郎 | |
| 屋山太郎会長を悼む | 古森義久 | |
| 時事通信の「坂の上の雲」 | 名越建郎 | |
| 屋山太郎先生の逝去を惜しむ | 丹羽文生 | |
| 日米の絆ー同盟から教育までー | 古森義久 | |
| 主催者挨拶 | 島田和久 | |
| 《基調講演》 | 我が国の防衛と安全保障 | 小野寺五典 |
| 《講 演》 | 国家保守主義(NatCon)と反グローバル化の世界的潮流 | 坂場三男 |
| 《講 演》 | プーチン政権5期目とウクライナ戦争の行方 | 名越健郎 |
| 《講 演》 | いま「国体」を考える | 村上政俊 |
| 《オープンディスカッション》 |
〈モデレーター〉 |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| 坂場三男 | ||
| 李相哲 | ||
| 空しい志位氏の自画自賛 | 筆坂秀世 | |
| 【特別研究】 |
||
| 藤谷昌敏 | ||
| 橋本量則 | ||
| 増永真悟 | ||
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 |
||
| 台湾海峡危機政策シミュレーションの意義 | 髙見澤將林 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第179回~181回 報告 | 長野禮子 |
|
| 【推薦図書】 | 推薦図書 | |
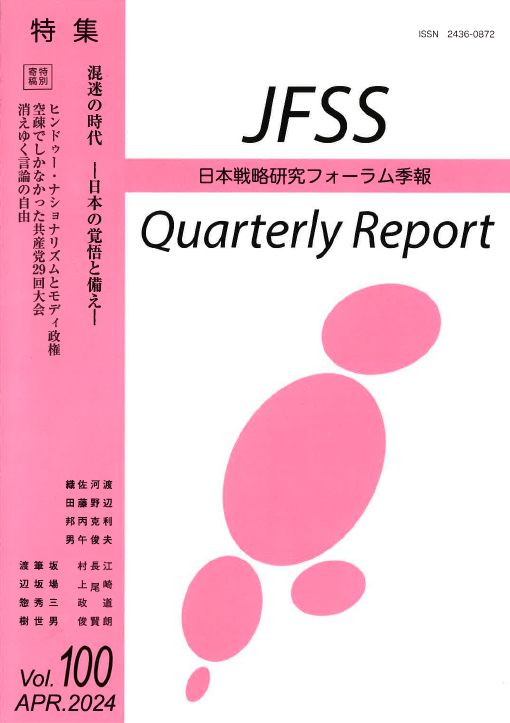
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 10年を迎えた中国の「一帯一路」 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 丹羽文生 | |
| 【特集】 混迷の時代 ー日本の覚悟と備えー | ||
| 渡辺利夫 | ||
| 混迷の時代ー日本の覚悟と備えー | 河野克俊 | |
| 日本の覚悟と備え | 佐藤丙午 | |
| 激動する国際情勢と日本の課題 | 織田邦男 | |
| 「有事」対応を進める日本 | 江崎道朗 | |
| 日本は、大国化するインドとどう付き合うべきか | 長尾賢 | |
|
村上政俊 |
||
| 【特別寄稿】 | ||
| ヒンドゥー・ナショナリズムとモディ政権 | 坂場三男 | |
| 筆坂秀世 | ||
| 消えゆく言論の自由 |
渡辺惣樹 | |
| 西村金一 | ||
|
アンドリュー・ オーチャード |
||
| (Eng.) |
Andrew Orchard |
|
| 【特別研究】 |
||
| 日本のセキュリティ・クリアランス制度と課題ー米国のセキュリティ・クリアランス制度を参考にしてー | 藤谷昌敏 | |
| 紅海危機にみる海洋地政学の重要性 | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 |
||
| 第12回 行為する者 | 岡部俊哉 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第178回 報告 | 長野禮子 |
|
| 【推薦図書】 | 推薦図書1 | |
| 推薦図書2 | ||
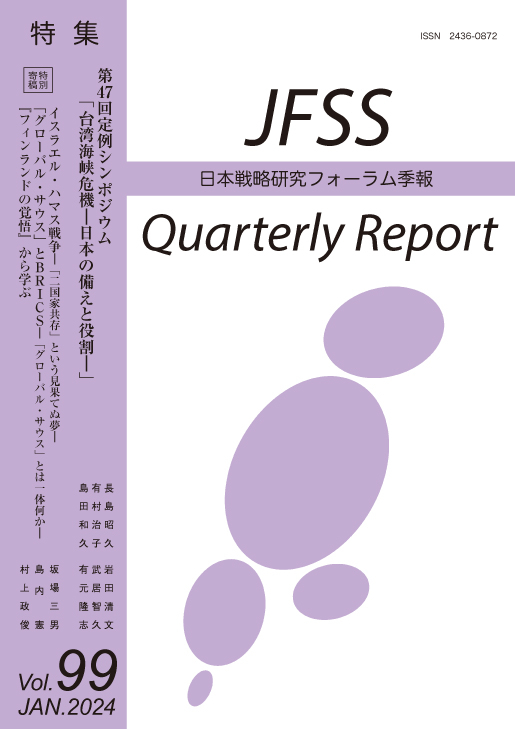
― 目次 ―
| 新年を迎えて | 憲法改正を急げ! | 屋山太郎 |
| 自らを助くる努力 |
島田和久 | |
| 巻頭言 | 日露戦争と脇光三 | 丹羽文生 |
| 《オープンディスカッション》 パネラー:長島昭久氏、有村治子氏、島田和久氏、岩田清文氏、武居智久氏 |
モデレーター 有元隆志 |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| 坂場三男 | ||
|
島内 憲
|
||
|
筆坂秀世
|
||
|
鬼塚隆志
|
||
|
西村金一
|
||
|
村上政俊
|
||
| 【特別研究】 | ||
| 藤谷昌敏 | ||
| 橋本量則 | ||
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 武力攻撃事態における国民保護について | 内山哲也 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第176~177回 報告 | 長野禮子 |
|
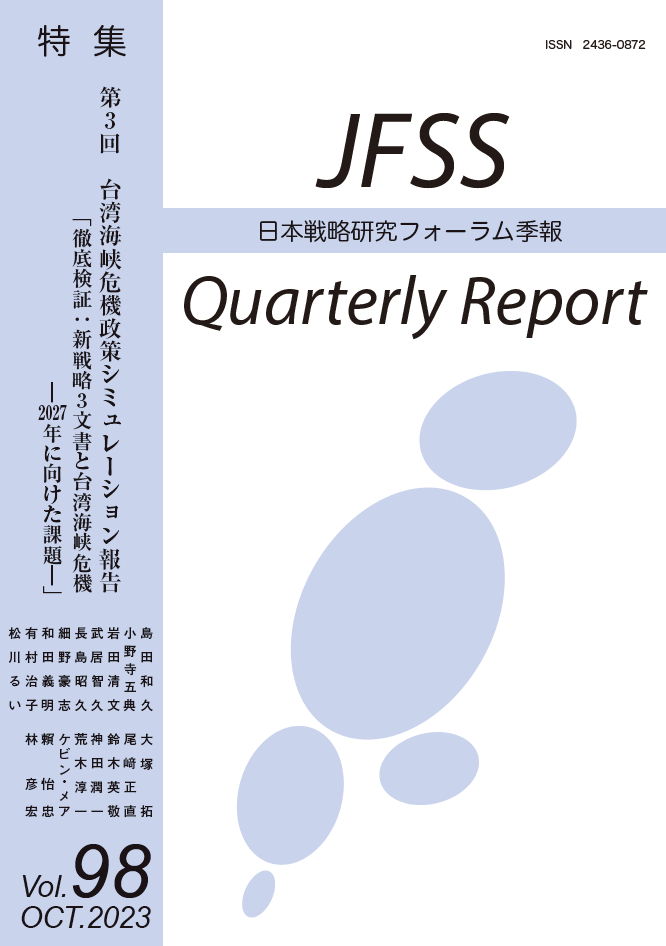
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 移民による文化摩擦と国家の崩壊 | 渡辺利夫 |
| 巻頭言 | 二宮尊徳と報徳思想 |
丹羽文生 |
|
|
||
| 島田和久 | ||
| 第3回政策シミュレーションから導き出されたこと ―小野寺氏・岩田氏・武居氏の鼎談― |
小野寺五典・ |
|
| 今後4年間こそが決定的に重要だ | 長島昭久 | |
| 総務大臣役を担当し痛感した残された課題 | 細野豪志 | |
| 第3回 台湾海峡危機政策シミュレーション ―外務大臣役を担って― |
和田義明 | |
| 「国土交通大臣」役を務め、台湾有事を警戒し、リスクを軽減するために具体的に検討したいこと | 有村治子 | |
| 第3回台湾海峡危機シミュレーションについての感想 | 松川るい | |
| 第3回台湾海峡危機政策シミュレーションを終えて | 大塚 拓 | |
| 鍵となる国内世論 ―経済面の分析を深め、戦略的コミュニケーションの進展を― |
尾﨑正直 | |
| 「台湾有事」は「経済有事」に直結 更に「経済有事」は先に来る ―官民挙げた備えの深化を― |
鈴木英敬 | |
| 台湾有事の際の財政・金融・経済分野における課題 | 神田潤一 | |
| JFSS 第3回政策シミュレーションに参加して | 荒木淳一 | |
| 台湾海峡危機政策シミュレーションから得られた教訓 | ケビン・メア | |
| (Eng.) | Lessons Learned from the Taiwan Crisis Simulation | Kevin K. Maher |
| 「台海有事即日本有事」的日本兵推觀察 ―安保三文件發表後的新局勢― |
賴 怡忠 | |
| 台湾から見た世界初の日米台 ―「台湾有事は日本有事」シミュレーションの感想― |
林 彦宏 | |
| 第3回政策シミュレーション―写真集― | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| コロナ後のベトナムと日越関係の行方 | 坂場三男 | |
| 「革命政党宣言」の裏には何があるのか | 筆坂秀世 | |
| 【特別研究】 | ||
| 新幹線技術の流出はどれほど日本の国益を損失させたのか ―中国の世界覇権に利用された日本の技術力― |
藤谷昌敏 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第10回 我が国のエネルギー安全保障における液化天然ガス(LNG)の課題 |
渡邉剛次郎 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第172~175回報告 | 長野禮子 |
|
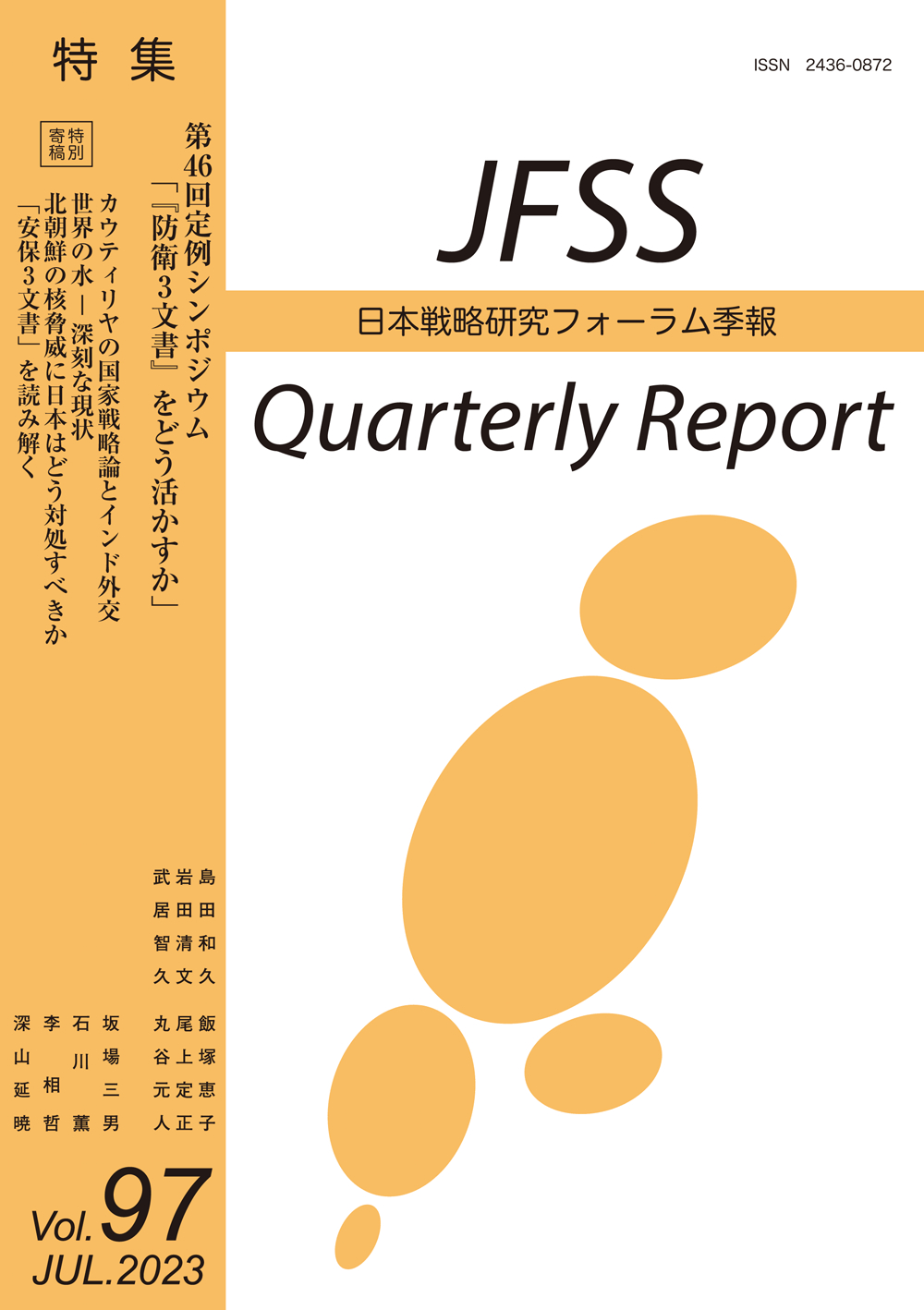
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 政治家に求められる武士道精神 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 丹羽文生 | |
| 【特集】第46回 定例シンポジウム報告 「『防衛3文書』をどう活かすか」 |
||
| モデレーター 尾上定正 |
||
| 【特別寄稿】 | ||
| カウティリヤの国家戦略論とインド外交 | 坂場三男 | |
| 世界の水-深刻な現状 | 石川 薫 | |
| 北朝鮮の核脅威に日本はどう対処すべきか | 李 相哲 | |
| 「安保3 文書」を読み解く | 深山延暁 | |
| 切羽詰まってしまった日本共産党 | 筆坂秀世 | |
| 政治家とノブレス・オブリージュ | 平井宏治 | |
| 【特別研究】 | ||
| 台湾の平和は日本の平和 | 武居智久 | |
| 藤谷昌敏 | ||
| 「防衛3 文書」に基づく施設整備に関する提言 |
長野俊郎 | |
| サウト・モハメド | ||
| 橋本量則 | ||
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第9回 能動的サイバー防御と通信の秘密 | 住田和明 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第169~171回 報告 | 長野禮子 | |
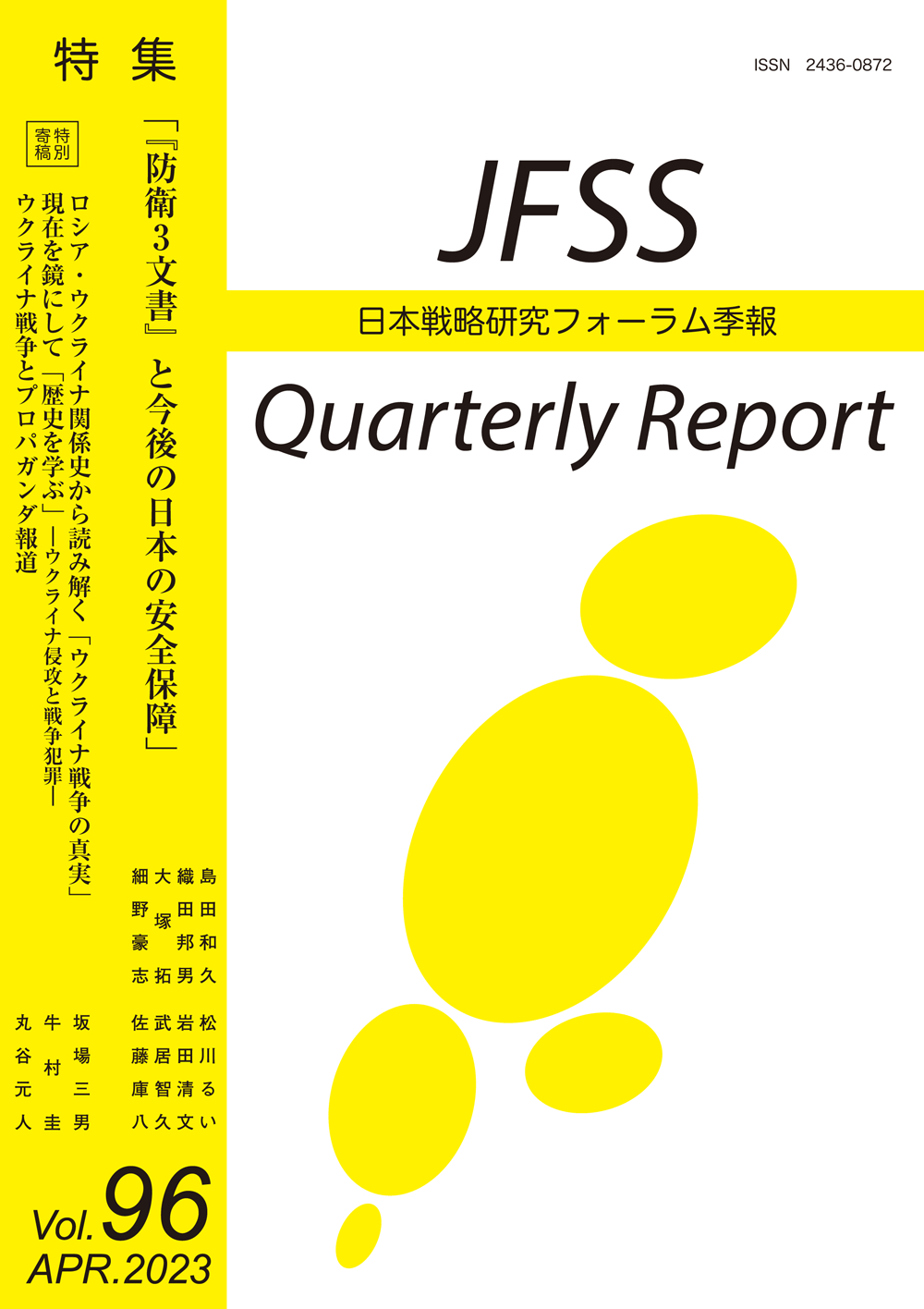
― 目次 ―
| 巻頭言 | 丹羽文生 | |
| 【特集】「『防衛3文書』と今後の日本の安全保障」 | ||
| 基盤的防衛力構想の影響とその終焉 | 島田和久 | |
| 織田邦男 | ||
| 防衛3文書と今後の日本の安全保障 | 大塚 拓 | |
| 戦後初めて安全保障の危機認識で国民が政治の先を行く | 細野豪志 | |
| 国家安保戦略を「日本の第三の自己変革」のはじまりに | 松川るい | |
| 戦略3文書具現化、国全体が本気度を示せ | 岩田清文 | |
| 武居智久 | ||
| 佐藤庫八 | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| 坂場三男 | ||
| 筆坂秀世 | ||
| 牛村 圭 | ||
| ウクライナ戦争とプロパガンダ報道 | 丸谷元人 | |
| 長尾 賢 | ||
| 平井宏治 | ||
| 【特別研究】 | ||
| 藤谷昌敏 | ||
| 海洋国家への歴史の教訓 ―地政学の視点から― |
寺井 融 | |
| 1930年代の日英関係 ―タイムズ紙が伝えた日本― | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第8回 台湾有事 ―日本に不可欠のシミュレーションとは― | 中村 進 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第167~168回 報告 | 長野禮子 |
|
| 推薦図書 | 推薦図書 | |
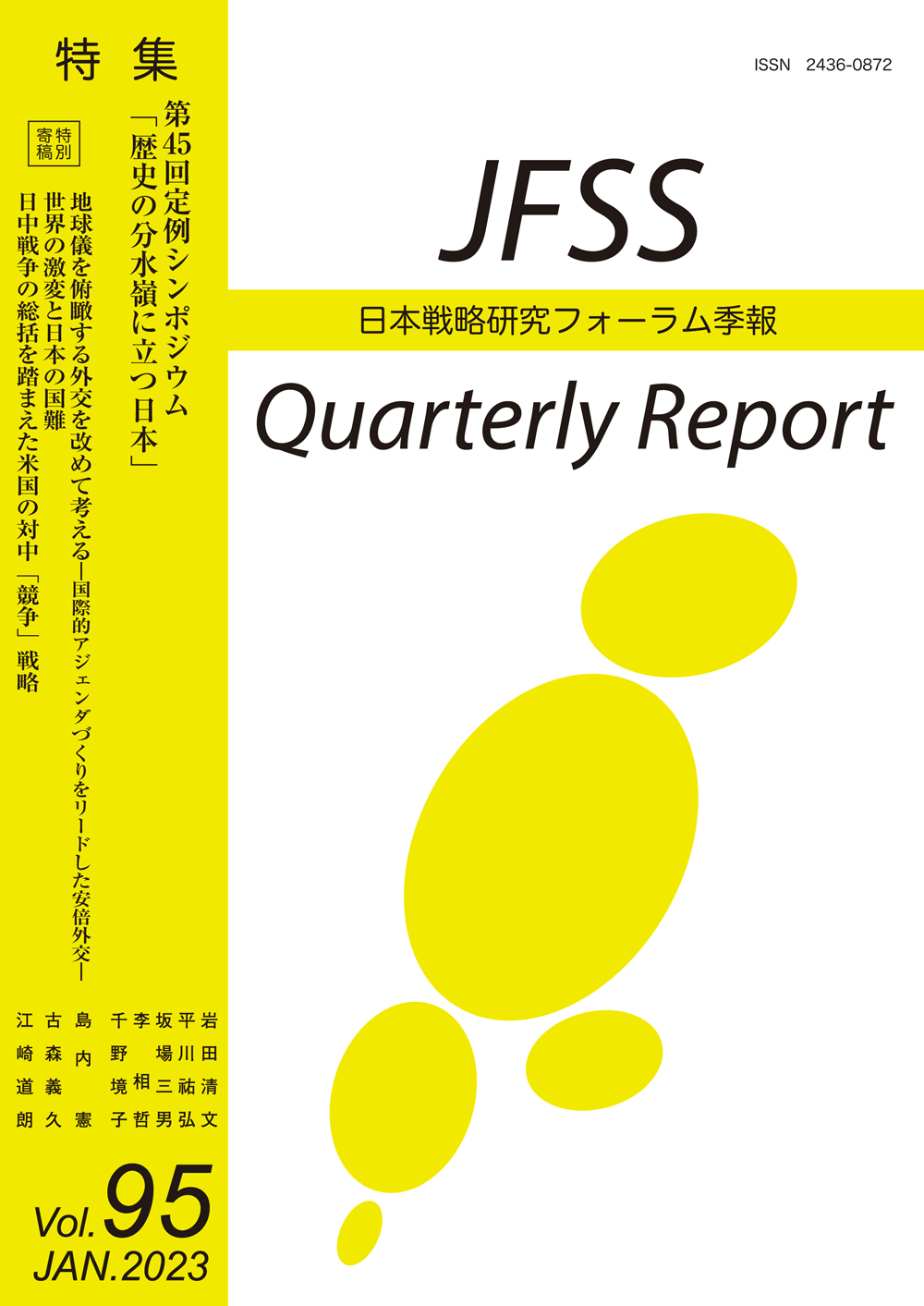
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 「一つの中国」を求める中国、健全な国の形示せ | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 「日中共同声明」を再確認せよ | 丹羽文生 |
| 《報 告》 | 第2回 台湾有事政策シミュレーション | 岩田清文 |
| 《基調講演》 | 歴史の分水嶺としての「脱亜入欧」 | 平川祐弘 |
| 《講 演》 | 東アジアにおける合従・連衡の虚実 | 坂場三男 |
| 日本の進路について決断する時 | 李 相哲 | |
| これからの日本 ―何を為すべきか― | 千野境子 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 島内 憲 | ||
| 世界の激変と日本の国難 | 古森義久 | |
| 日中戦争の総括を踏まえた米国の対中「競争」戦略 | 江崎道朗 | |
| 中国の習近平体制と露わになった中国共産党の特質 | 筆坂秀世 | |
| 中国の監視カメラで監視される日本 | 平井宏治 | |
| サウト・モハメド | ||
| 【特別研究】 | ||
| 東ロシア暗殺の系譜、政治・社会の後進性と人命軽視 | 藤谷昌敏 | |
| 海洋国家への歴史の教訓 ―地政学の視点から― | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第7回 急がれる事態対処法の見直しを含む法的整備の充実 | 髙田克樹 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第165~166回 報告 | 長野禮子 | |
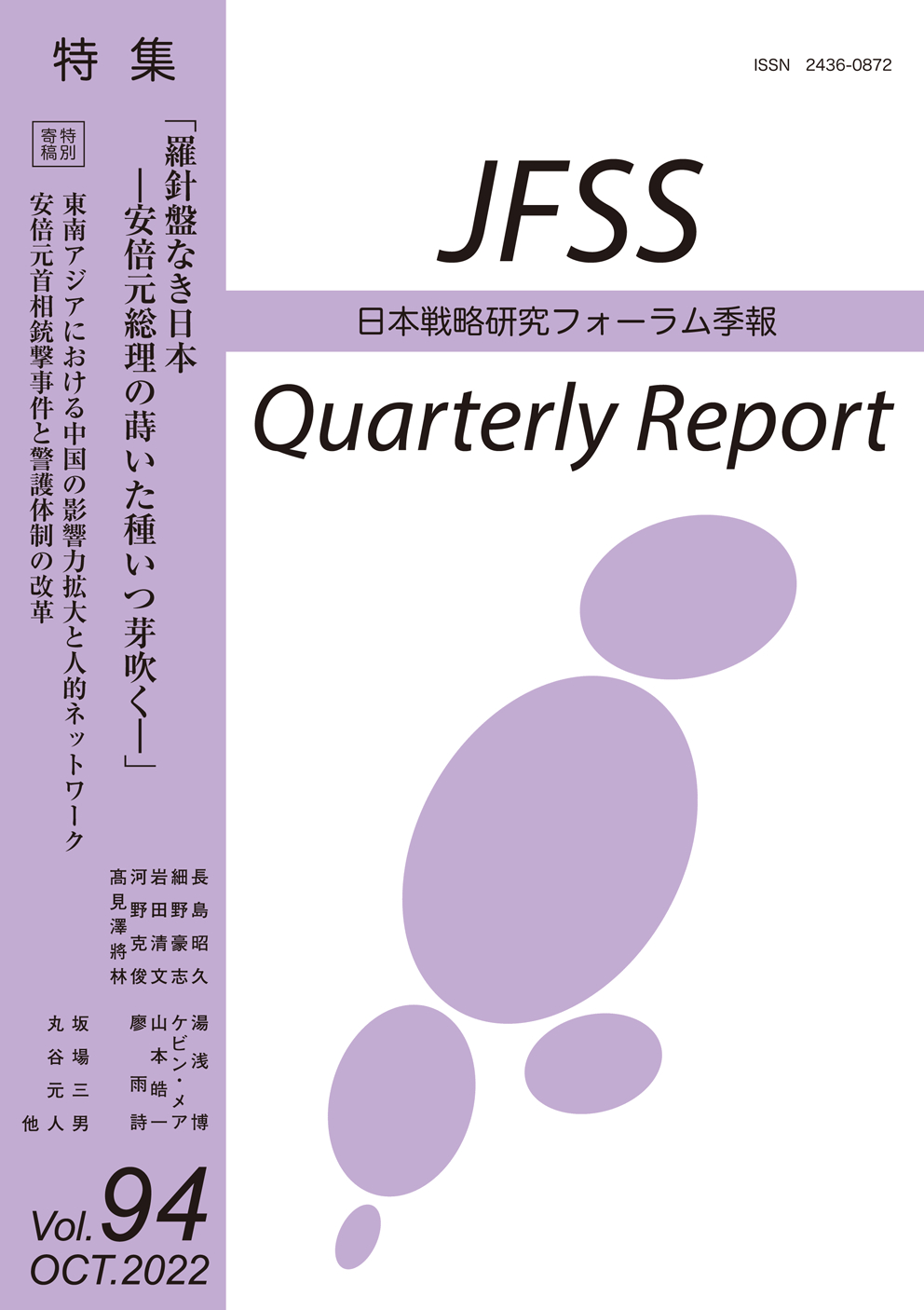
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 安倍晋三という政治家 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 「安倍不在」の日本 | 丹羽文生 |
| 【特集】「羅針盤なき日本 ―安倍元総理の蒔いた種いつ芽吹く―」 | ||
| 「戦後レジームからの脱却」を完結 | 長島昭久 | |
| 次の世代に自由で民主的な日本を引き継ぐために | 細野豪志 | |
| 安倍晋三元総理の遺志こそが日本の羅針盤 | 岩田清文 | |
| 羅針盤なき日本の未来―今後の日本の安全保障 | 河野克俊 | |
| 「国の形」を実装し、課題に正面から総力を挙げて取り組む政治に期待する | 髙見澤將林 | |
| 安倍戦略を引き継ぎ全体主義と闘え | 湯浅 博 | |
| 安倍氏の遺産 ―ワシントンからの視点― | ケビン・メア | |
| 安倍晋三さんと私 | 山本皓一 | |
| ポスト安倍時代 台日関係はどう進むか | 廖 雨詩 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 東南アジアにおける中国の影響力拡大と人的ネットワーク | 坂場三男 | |
| 安倍元首相銃撃事件と警護体制の改革 | 丸谷元人 | |
| 科学・技術の国家戦略を考えるために ―補遺:科学・技術と軍事研究について― |
武田 靖 | |
| 上海電力日本による電力産業への参入問題 | 平井宏治 | |
| 【特別研究】 | ||
| 経済安全保障の根幹、重要技術流出のリスク ―経済インテリジェンスの脅威― |
藤谷昌敏 | |
| 海洋国家と宗教―歴史の視点からの一考察― | 橋本量則 | |
| 【報告】第2回 政策シミュレーション 「徹底検証:台湾海峡危機 日本はいかに備えるべきか」の成果概要 |
||
| 第2回台湾有事シミュレーションに参加して | 兼原信克 | |
| 第2回台湾有事シミュレーションの概要 | JFSS事務局 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第6回 日本は侵略に抵抗できるか | 村井友秀 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第162~164回 報告 | 長野禮子 | |
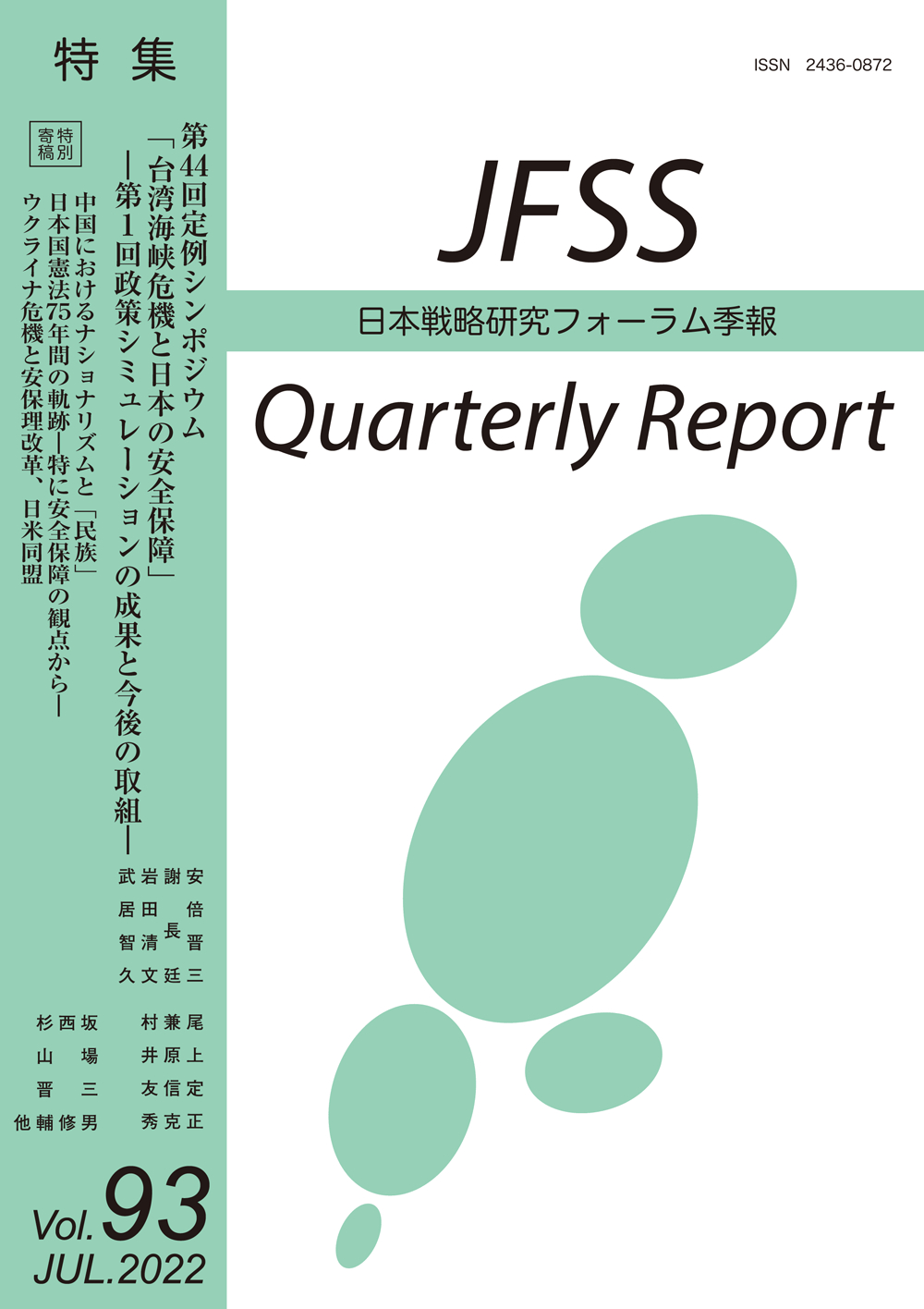
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 変化の兆しを見せる日本の政界地図 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 鎮魂の8月を前に―戦禍に斃れた「元日本人戦没者」― | 丹羽文生 |
| 追 悼 | 故葛西さんを悼む | 屋山太郎 |
| 【特集】第44回 定例シンポジウム報告 「台湾海峡危機と日本の安全保障」 ―第1回政策シミュレーションの成果と今後の取組― |
||
| 《基調講演》 | 台湾海峡危機と日本の安全保障 ―日本のなすべきこととは― |
安倍晋三 |
| 《基調講演》 | 自分の国は自分で守る | 謝 長廷 |
| 第1 回政策シミュレーション 「徹底検証:台湾海峡危機 日本はいかに抑止し対処すべきか」 |
||
| 開催目的と概要説明 | 岩田清文 | |
| 台湾海峡危機政策シミュレーションのフォローアップ | 武居智久 | |
| 《オープンディスカッション》 政策シミュレーションコアメンバー:岩田清文氏・武居智久氏・兼原信克氏・村井友秀氏・尾上定正氏によるディスカッション |
モデレーター 田北真樹子 |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| 中国におけるナショナリズムと「民族」 | 坂場三男 | |
| 日本国憲法75年間の軌跡―特に安全保障の観点から― | 西 修 | |
| ウクライナ危機と安保理改革、日米同盟 | 杉山晋輔 | |
| ウクライナ危機:トルコ外交の強かさ | 渡辺惣樹 | |
| ウクライナ戦争から日本は何を学ぶのか | 織田邦男 | |
| ウクライナ戦争に覚醒せよ | 岩田清文 | |
| 科学・技術の国家戦略を考えるために ―第三の立国のために― |
武田 靖 | |
| 【特別研究】 | ||
| 経済安全保障はなぜ必要なのか ―反対意見に反論する― |
藤谷昌敏 | |
| 国防と世界観―思想が国際関係に及ぼす影響― | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第5回 ウクライナ戦争の教訓 | 兼原信克 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第160~161回 報告 | 長野禮子 | |
| 推薦図書 | 推薦図書 | |
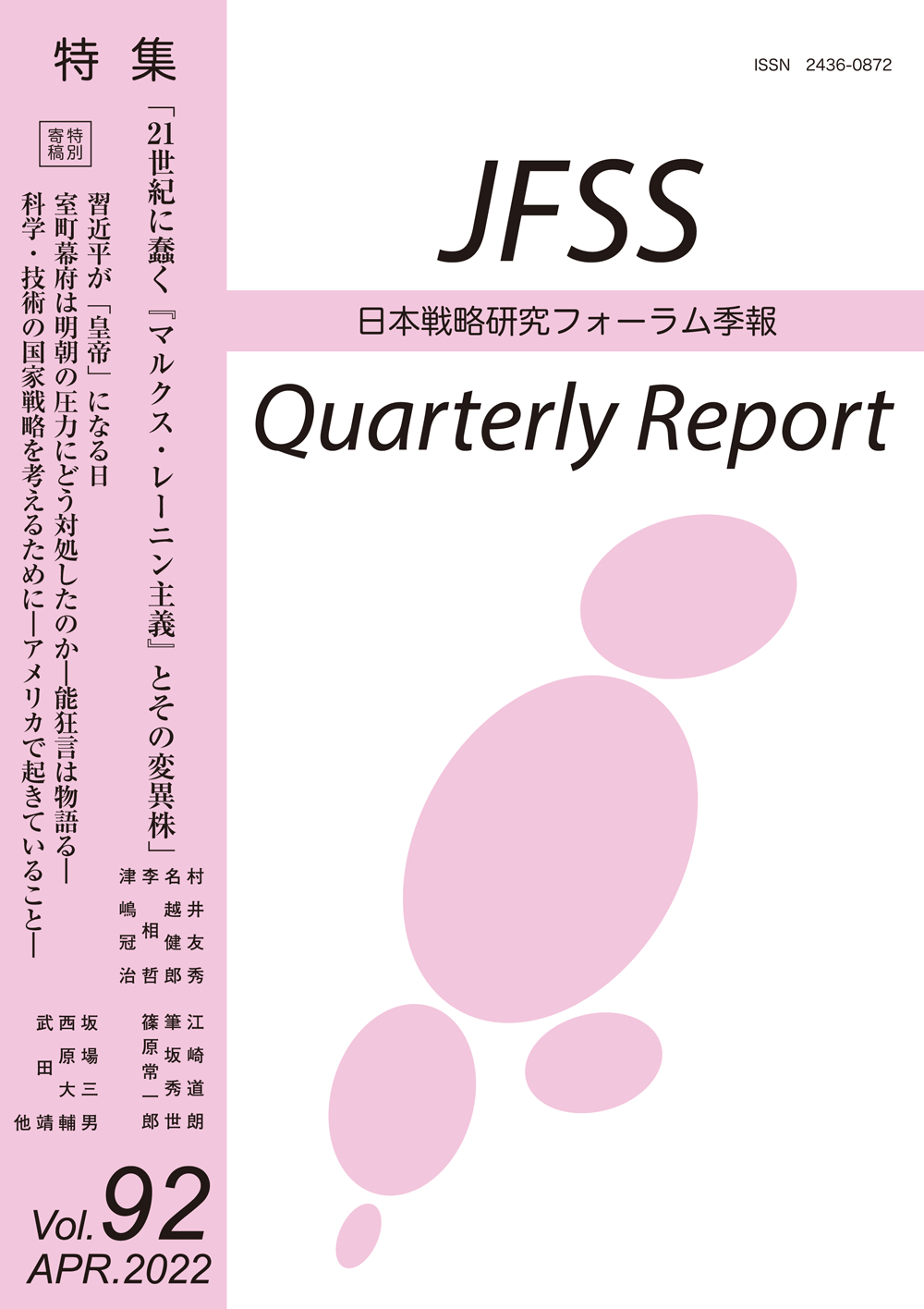
― 目次 ―
| 会長挨拶 | ウクライナ侵攻と台湾奪取の違い | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 台湾侵攻に根拠なし | 丹羽文生 |
| 【特集】「21世紀に蠢く『マルクス・レーニン主義』とその変異株」 | ||
| 中国は戦争をするのか | 村井友秀 | |
| ウクライナ危機はソ連崩壊の残滓 ―プーチンらKGB同僚が攻撃決定か― |
名越健郎 | |
| 私はマルクスをどう学んだか ―「マルクス・レーニン主義」批判に代えて― |
李 相哲 | |
| ルーマニアにおける「共産主義の残滓」と「新たなロシアの脅威」 | 津嶋冠治 | |
| 国連発の家族解体政策に警戒を | 江崎道朗 | |
| マルクス・レーニン主義こそが最大の変異株 | 筆坂秀世 | |
| “21世紀世界制覇”目指す「シン・共産主義革命工作」―中国の「サイレント・インベージョン」とマルクス主義変異株の運動― | 篠原常一郎 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 習近平が「皇帝」になる日 | 坂場三男 | |
| 室町幕府は明朝の圧力にどう対処したのか ―能狂言は物語る― |
西原大輔 | |
| 科学・技術の国家戦略を考えるために ―アメリカで起きていること― |
武田 靖 | |
| VIE スキームとは何か ―日本企業が中国企業をM&Aできない仕組みを解説する― | 平井宏治 | |
| 「ウクライナ侵攻の背景」―民間多国籍調査チームによる現場情報分析の視点から― | 野田敬司 | |
| 「霊戦」:日米戦争を踏まえて米ソ「冷戦」の再考を | ジェイソン M. モーガン |
|
| 【特別研究】 | ||
| ウクライナで仕掛けるロシアのハイブリッド戦 | 藤谷昌敏 | |
| 極超音速ミサイルの技術は東北大学から流出した | 平井宏治 | |
| 国防と文化―保田與重郎と三島由紀夫の見た風みやび雅の道― | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第4回 ウクライナ戦争と台湾 | 尾上定正 | |
| 推薦図書 | 推薦図書 |
|
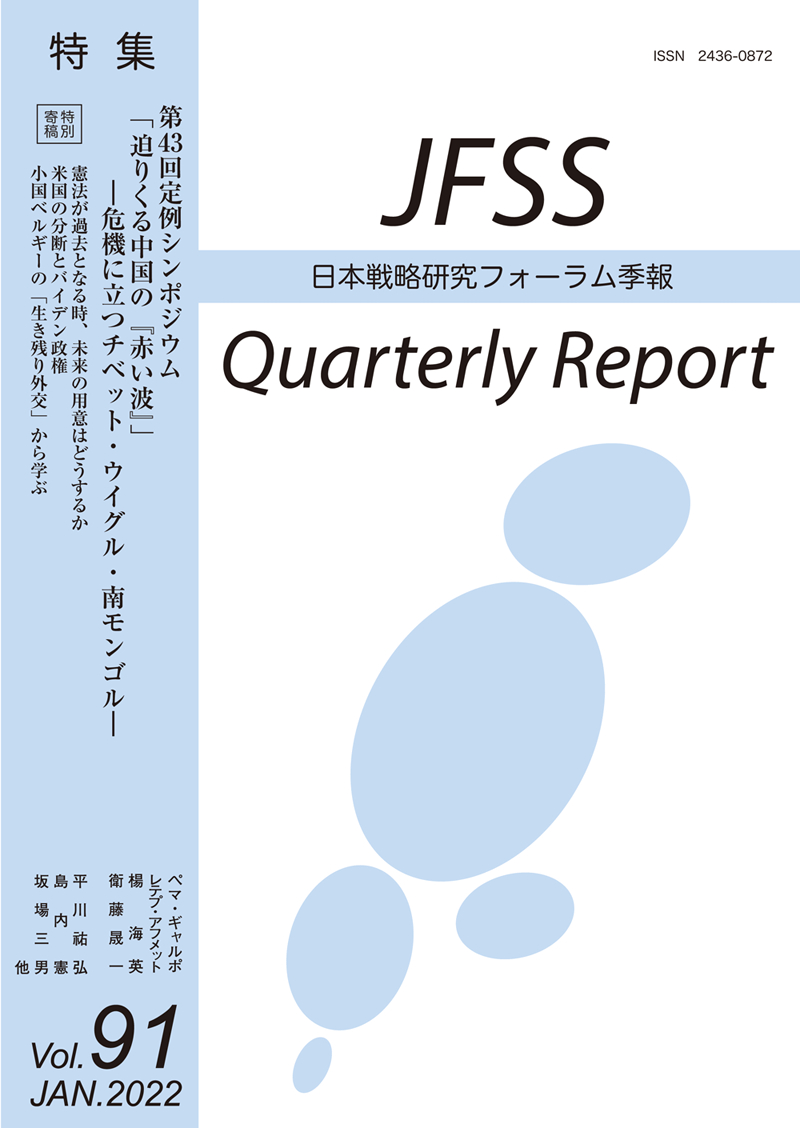
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 今年の政治展望 | 屋山太郎 |
| 最高顧問就任挨拶 | 安倍晋三 | |
| 巻頭言 | 断交半世紀と今後の日台関係 | 丹羽文生 |
| 【特集】第43回 定例シンポジウム報告 「迫りくる中国の『赤い波』」 ―危機に立つチベット・ウイグル・南モンゴル― |
||
| 《講 演》 | チベットにおける中国の民族浄化政策 ―日本は何を学ぶべきか― |
ペマ・ギャルポ |
| 「ジェノサイド」及び「人道に対する罪」に認定されたウイグルの現状について | レテプ・アフメット | |
| 中国によるモンゴル人ジェノサイド―過去・現在― | 楊 海英 | |
| 《特別講演》 | 中国の人権問題に対する日本の取組と日本国再生への道 | 衛藤晟一 |
| 《オープンディスカッション》 | モデレーター 田北真樹子 |
|
| 【特別寄稿】 | ||
| 憲法が過去となる時、未来の用意はどうするか | 平川祐弘 | |
| 米国の分断とバイデン政権 | 島内 憲 | |
| 小国ベルギーの「生き残り外交」から学ぶ | 坂場三男 | |
| 新しい年の日本の国難、そして皇室 | 古森義久 | |
| 冷戦の終結と情報公開によって欧米で見直される近現代史 | 江崎道朗 | |
| 野党共闘はなぜ失敗したのか ―立憲民主党と日本共産党の敗北の理由― |
筆坂秀世 | |
| 科学・技術の国家戦略を考えるために ―立国は技術によるしかない― |
武田 靖 | |
| 2022年の印米関係 ―戦略的関係から完全なパートナーへ― |
ジャガンナートP. パンダ | |
| (Eng.) | From Strategic to Absolute Partners: Prospects for US-India ties in 2022 | Jagannath P. PANDA |
| 【特別研究】 | ||
| 世界に大きな影響を与える中国によるハニートラップ事件 | 藤谷昌敏 | |
| 国防と和歌に関する一考察 | 橋本量則 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第3回 戦前の台湾統治が残した倫理的な義務 | 武居智久 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第158~159回 報告 | 長野禮子 | |
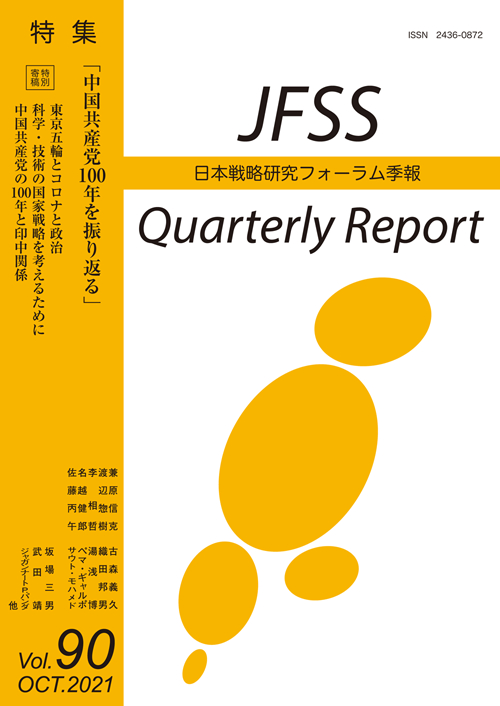
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 中国4000年の歴史に生き続ける宗族イズム | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 読書の秋に思うこと ―「偉大な指導者」は「偉大な読書家」― |
丹羽文生 |
| 【特集】「中国共産党100年を振り返る」 | ||
| 中国共産党の挫折と中国の将来 | 兼原信克 | |
| 1940年の米大統領選挙と宋美齢 | 渡辺惣樹 | |
| 日本は中国との長期戦に備えよ | 李 相哲 | |
| 中露関係100年、「準同盟」は日本外交に脅威 | 名越健郎 | |
| 米中関係の戦略的考察 | 佐藤丙午 | |
| 中国共産党とその敵 ―百年史でのアメリカとのかかわり― |
古森義久 | |
| 中国共産党創設100年と日本の課題 | 織田邦男 | |
| 大国間競争の「対中シフト」恐れる中国 | 湯浅 博 | |
| チベット解放(侵略)70年 ―「文化的ジェノサイド」が繰り広げられる我が祖国― | ペマ・ギャルポ | |
| 東トルキスタン共和国の崩壊と新疆ウイグル自治区の成立 | サウト・モハメド | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 東京五輪とコロナと政治 | 坂場三男 | |
| アフガン政権崩壊を巡る米国内の議論の現状 | 吉田正紀 | |
| 中国共産党と蜜月、断絶を繰り返してきた日本共産党 | 筆坂秀世 | |
| 科学・技術の国家戦略を考えるために | 武田 靖 | |
| 規制と統制を強める中国政府 | 平井宏治 | |
| 1年遅れのTOKYO 2020を終えて | 牛村 圭 | |
| 中国共産党の100年と印中関係 | ジャガンナートP. パンダ | |
| (Eng.) | Chinese Communist Party Centenary and India-China Relations | Jagannath P. PANDA |
| 【特別研究】 | ||
| 中国共産党の暗部、香港市民を弾圧する秘密結社「三合会」 | 藤谷昌敏 | |
| 不祥事に揺れる東芝を「日米共同監視企業」にするべき理由 | 平井宏治 | |
| (Eng.) | Scandalous Toshiba to be Japan-U.S. Joint Surveillance Company | HIRAI Koji |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第2回「台湾有事研究会発足への思いと政策シミュレーション準備」 | 岩田清文 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第156~157回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
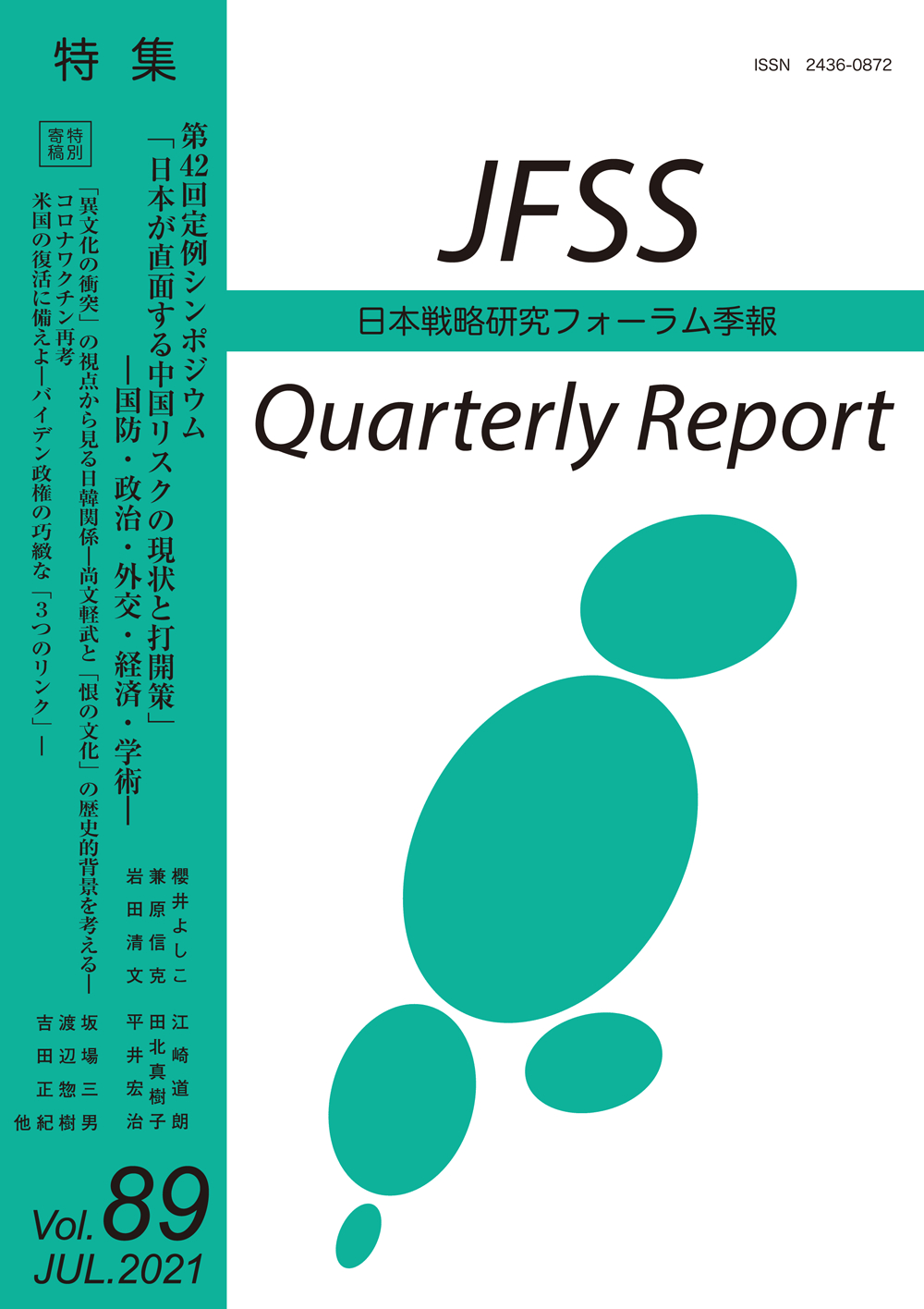
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 台湾海峡波高し | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 新渡戸稲造とSDGs | 丹羽文生 |
| 【特集】第42回 定例シンポジウム報告 「日本が直面する中国リスクの現状と打開策」 ―国防・政治・外交・経済・学術― |
||
| 《講 演》 | 米中関係の真ん中にいる日本の果たすべき役割 | 櫻井よしこ |
| 中国の台頭と台湾有事のリアル | 兼原信克 | |
| 中国の脅威に日本はどう備えるべきか ―中台紛争は日本有事― |
岩田清文 | |
| 対中国情報戦と我が国のインテリジェンス | 江崎道朗 | |
| 巧妙化する中国のプロパガンダ工作 | 田北真樹子 | |
| 経済安全保障(Economic Statecraft)における中国リスク | 平井宏治 | |
| ≪オープンディスカッション・質疑応答≫ | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| 「異文化の衝突」の視点から見る日韓関係 ―尚文軽武と「恨の文化」の歴史的背景を考える― |
坂場三男 | |
| コロナワクチン再考 | 渡辺惣樹 | |
| 米国の復活に備えよ ―バイデン政権の巧緻な「3つのリンク」― |
吉田正紀 | |
| 日本共産党を含む野党共闘のもろさ | 筆坂秀世 | |
| 我が国は国を挙げて半導体産業を再興せよ | 平井宏治 | |
| 宇宙利用の不安定要因と国際連携の必要性 ―サイバーセキュリティは中心的な課題― |
渡辺秀明 | |
| クアッドにおける印米関係の発展 | ジャガンナートP. パンダ | |
| (Eng.) | Taking Forward the India-US Ties in the Quad Framework | Jagannath P. PANDA |
| 李栄薫『反日種族主義との闘争』(文藝春秋、2020年) | ジェイソン モーガン |
|
| (Eng.) | Review of Lee Young-hoon, et al., eds., Han-Nichi Shuzokushugi to no Tōsō (My fi ght against anti-Japan tribalism)(Tokyo: Bungei Shunju, 2020) | Jason Morgan |
| 【特別研究】 | ||
| 情報機関の見えざる手、世界を動かした黒子たち ―対日最後通牒ハル・ノートの原案を作成した元米国財務次官補ハリー・デクスター・ホワイト― |
藤谷昌敏 | |
| 新たな戦い方「モザイク戦」の特徴と今後の方向性 | 下平拓哉 | |
| 【リレーエッセイ 百家争鳴】 | ||
| 第1回「台湾有事研究会」の発足 | 佐藤裕視 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第154~155回 報告 | 長野禮子 | |
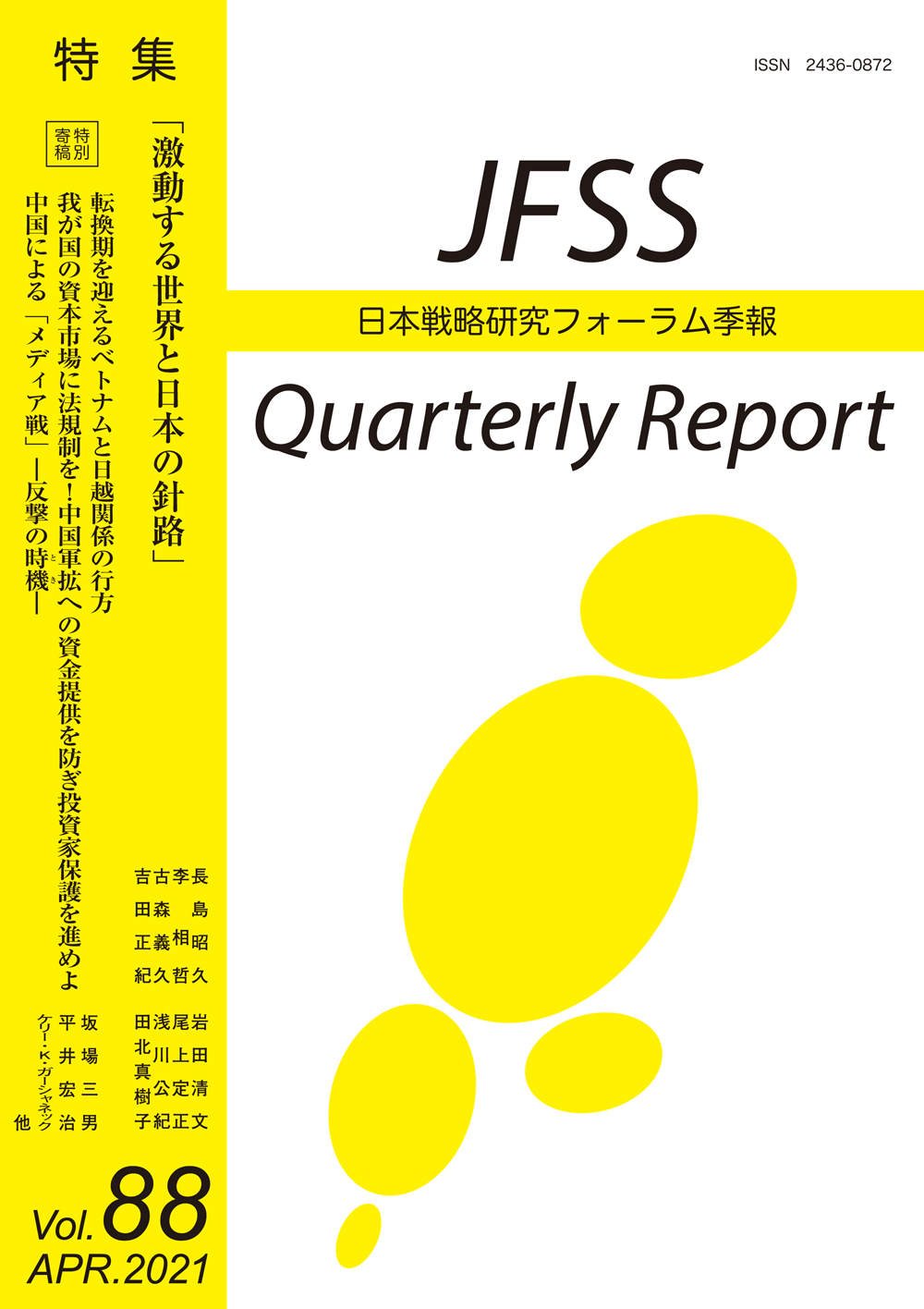
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 中国孤立化の流れは止まらない | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 岩倉使節団に学ぶ | 丹羽文生 |
| 【特集】「激動する世界と日本の針路」 | ||
| 米中「新冷戦」下における我が国の安全保障戦略 | 長島昭久 | |
| 日本は文在寅後の対韓国戦略を考えよ | 李 相哲 | |
| バイデン政権:静かな船出 ―甘すぎる?「ハネムーン」の背景― |
吉田正紀 | |
| バイデン新政権下の米中関係と日本の国難 | 古森義久 | |
| 重大な岐路に立つ日本、今こそ生き様を定める時 | 岩田清文 | |
| バイデン2045年の日本に向けて | 尾上定正 | |
| 新しい戦争に備えよ | 浅川公紀 | |
| 真の防備は心理的な中国克服から | 田北真樹子 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 転換期を迎えるベトナムと日越関係の行方 | 坂場三男 | |
| 北方領土と尖閣問題で今考える事 | 筆坂秀世 | |
| 中国軍拡への資金提供を防ぎ投資家保護を進めよ | 平井宏治 | |
| 2020年12月9日NHK BSP放映番組「昭和の選択 太平洋戦争 東条英機 開戦への煩悶」について | 副島豊次郎 | |
| 米国主導のクアッド首脳会議が意味するもの | ジャガンナートP. パンダ | |
| (Eng.) | What does a US-led Quad leadership summit imply | Jagannath P. PANDA |
| 中国による「メディア戦」―反撃の時機― | ケリー・K・ガーシャネック | |
| (Eng.) | China's ‘Media Warfare': Time to Fight Back | Kerry K. GERSHANECK |
| 【特別研究】 | ||
| 中国を封じ込める太平洋の盾「クアッド構想」 | 藤谷昌敏 | |
| 正解のない新たな時代に求められる未来創造 ―渋沢栄一とピーター・ドラッカーに学ぶ― |
下平拓哉 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第151~153回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
| 推薦図書 | 推薦図書 | |
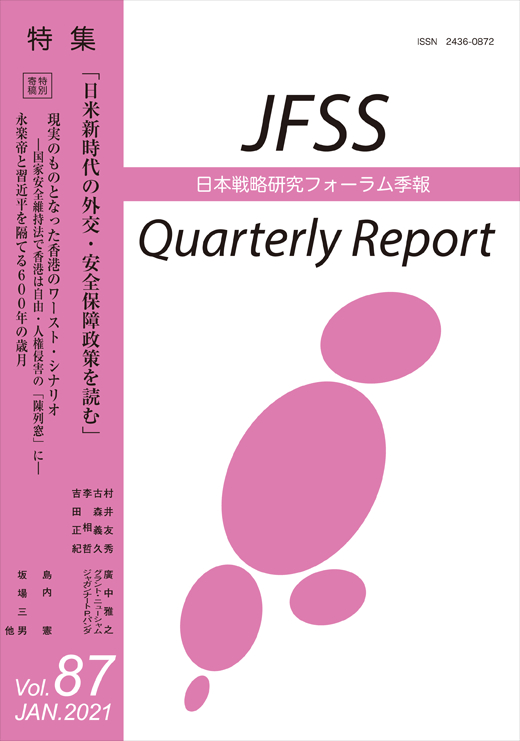
― 目次 ―
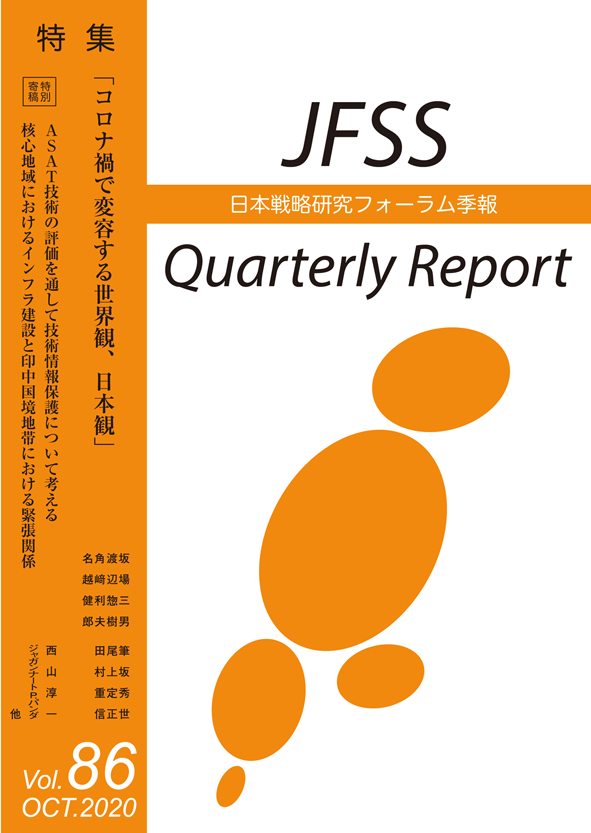
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 「世界をひっくり返した中国」―米中対立深刻化― | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 「朝鮮戦争の英雄」を偲ぶ | 丹羽文生 |
| 【特集】「コロナ禍で変容する世界観、日本観」 | ||
| ポスト・コロナの国際関係を読む3つの座標軸 | 坂場三男 | |
| コロナ後を考えるのはまだ早い | 渡辺惣樹 | |
| コロナ禍を転じて福となすために ―3つの課題― | 角﨑利夫 | |
| 安倍・プーチン交渉破綻の謎 | 名越健郎 | |
| 米中対決を“新冷戦”などとは呼べない ―中国にも、アメリカにもそれほどの権威はない― |
筆坂秀世 | |
| 米中「新冷戦」の軍事的評価 | 尾上定正 | |
| コロナ禍、日本の国家安全保障戦略・インテリジェンス・防衛政策を考える | 田村重信 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| ASAT技術の評価を通して技術情報保護について考える | 西山淳一 | |
| 核心地域におけるインフラ建設と印中国境地帯における緊張関係 | ジャガンナートP. パンダ | |
| (Eng.) | Infrastructure Build-Up at the Core and India-China Border Tensions | Jagannath P. Panda |
| オーエン・マッシューズ著『完璧なスパイ スターリンのマスターエージェント、リヒャルト・ゾルゲ』を読み説く | ジェイソンM. モーガン |
|
| (Eng.) | Review of Owen Matthews, An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin's Master Agent | Jason M. Morgan |
| 我是不是我的我(私は私でない私)―李登輝と西田哲学― | 陳永峰 | |
| 日本の戦略なきグローバル化 | 平井宏治 | |
| 【特別研究】 | ||
| 米朝交渉が進まない中で、北の核ミサイルが現実的な脅威となった ―北の核が使える兵器に進化し、増産中である― | 西村金一 | |
| 中国が展開する世界制覇戦略「超限戦」 | 藤谷昌敏 | |
| 新たな社会創造のためのイノベーション ―アディティブ・マニュファクチュアリングが変える「ものづくり」と社会― | 下平拓哉 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第140~143回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
| 推薦図書 | 推薦図書 | |
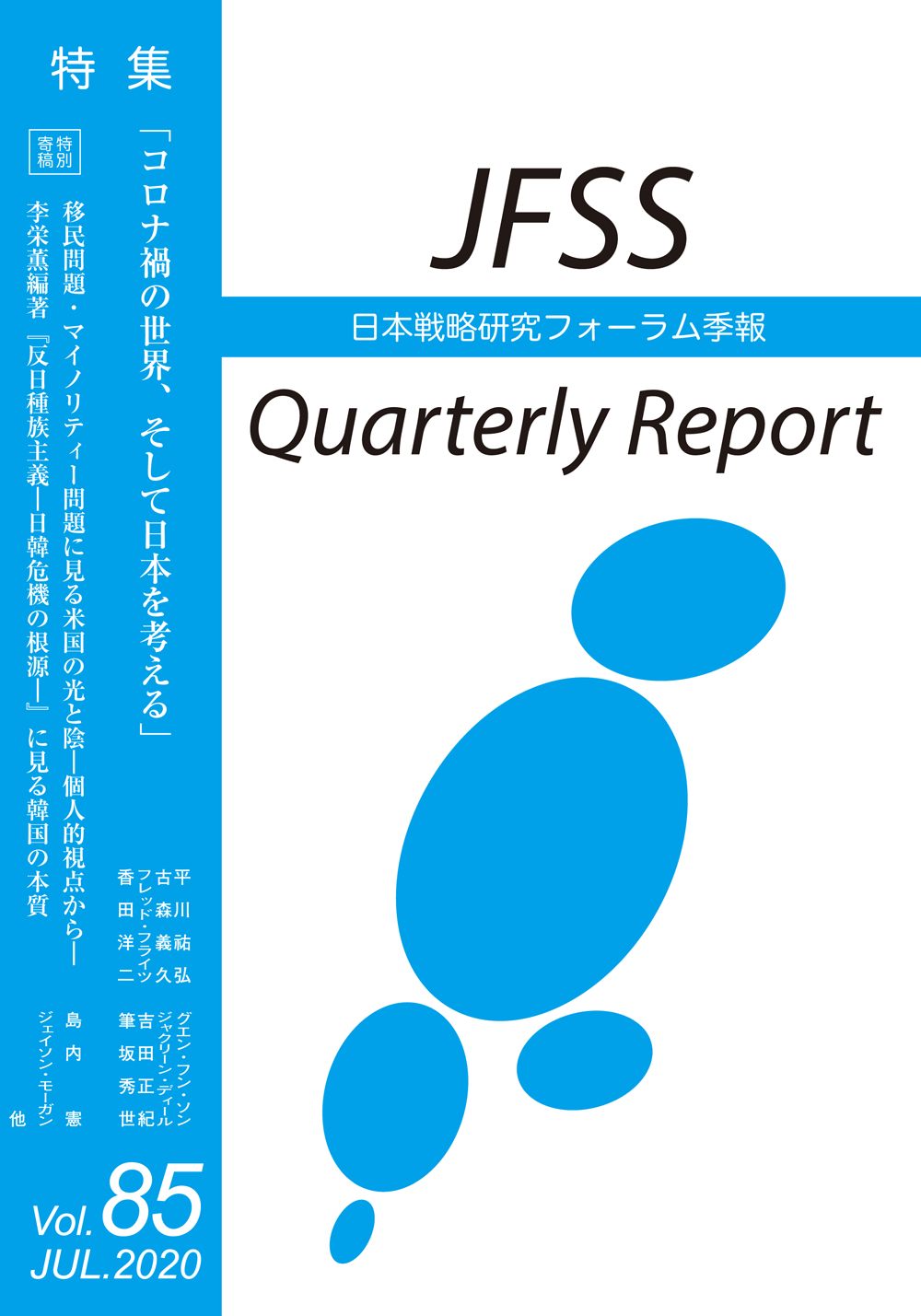
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 武漢発新型コロナウイルス騒ぎの本質と収束後の世界 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 中国「一帯一路」後退へ ―新型コロナウイルス禍による打撃― |
丹羽文生 |
| 【特集】「コロナ禍の世界、そして日本を考える」 | ||
| 日本国家の行方 | 平川祐弘 | |
| 中国ウイルスの国際拡散と日本の異端 | 古森義久 | |
| コロナ禍は米中関係をどう変えるのか | フレッド・フライツ | |
| (Eng.) | How the Coronavirus Pandemic Will Change U.S.-China Relations | Fred Fleitz |
| コロナ禍の陰で覇権拡大を狙う中国 | 香田洋二 | |
| ポストコロナの試金石としての南シナ海 | グエン・フン・ソン | |
| (Eng.) | The South China Sea as a test for the post Covid-19 order | Nguyen Hung Son |
| 日本と米国は準備しなければならない ―紛争に備えた控えめな中国包囲網― |
ジャクリーン・ ディール |
|
| (Eng.) | Preparing Japan and the United States: A Chastened China Girds for Conflict |
Jacqueline Deal |
| 戦時下の大統領を“演ずる”トランプ ―トランプ大統領が仕掛けた3つの戦い― |
吉田正紀 | |
| 中国は国家主権、人権、民主主義の敵 | 筆坂秀世 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 移民問題・マイノリティー問題に見る米国の光と陰 ―個人的視点から― |
島内 憲 | |
| 李栄薫編著『反日種族主義―日韓危機の根源―』に見る韓国の本質 | ジェイソン・モーガン | |
| (Eng.) | Lee Young-hoon et al.,“Anti-Japan Tribalism: The Root of the Korea-Japan Crisis” | Jason Morgan |
| 外資規制強化の背景と改正外為法の概要 | 平井宏治 | |
| 【特別研究】 | ||
| 金正恩委員長の死亡説の例から、情報分析ノウハウを解説する ―信頼できない情報筋からの情報に惑わされないこと― | 西村金一 | |
| 感染症が共産主義を生んだ、そして共産主義が感染症を生んだ ―マルクスの資本論と中国共産党が生んだ新型コロナウイルス― | 藤谷昌敏 | |
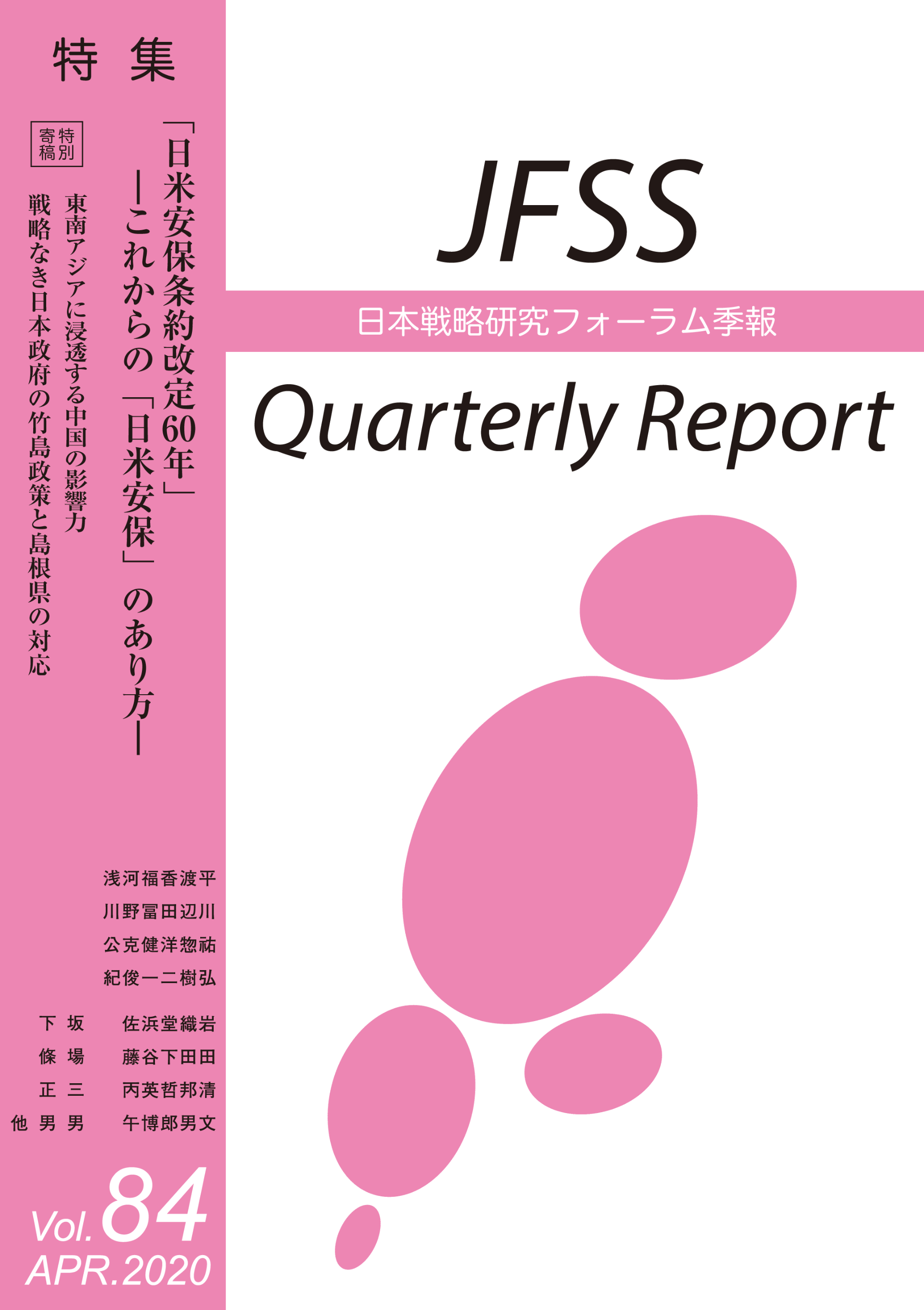
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 日米は自由と民主主義を追求する同志 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 蔣介石を祀る神社 ―台湾で進行する「去蔣化」― | 丹羽文生 |
| 追悼 | 芳賀徹追悼の辞― | 平川祐弘 |
| 【特集】「日米安保条約改定60年」 ―これからの「日米安保」のあり方― |
||
| これから何を備えるべきか | 平川祐弘 | |
| あの戦争を議論するためのいくつかの新視点 | 渡辺惣樹 | |
| 語られていない我が国防衛戦略(30防衛大綱)の深刻な問題点 | 香田洋二 | |
| 政局型「吉田ドクトリン」と理念型「岸ドクトリン」との相克と日米同盟 | 福冨健一 | |
| 今後の日米同盟のあり方 | 河野克俊 | |
| 日米安全保障体制の中の日本の展望 | 浅川公紀 | |
| 日米同盟を機能させるために | 岩田清文 | |
| これからの日米同盟の課題 ―キーワードは「双務性」と「自主防衛」― |
織田邦男 | |
| 変容する海の日米同盟:令和日本の課題 | 堂下哲郎 | |
| 新旧日米安保条約の特徴と日本の防衛 ―米国の対日防衛義務と米国戦争権限法条文相互の矛盾― | 浜谷英博 | |
| 日米安保条約の将来 ―特別な関係の先にあるもの― | 佐藤丙午 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 東南アジアに浸透する中国の影響力 | 坂場三男 | |
| 戦略なき日本政府の竹島政策と島根県の対応 | 下條正男 | |
| 首里城焼失の背景にある沖縄の「危うさ」 | 篠原 章 | |
| 米国の国防権限法に見る日本企業への影響 | 平井宏治 | |
| 【特別研究】 | ||
| 中国で、武漢ウイルスの発生と感染拡大の理由は ―新型肺炎を抑え込んでも、消滅させられない汚染源― |
西村金一 | |
| 北朝鮮帰国事業に対する日本政府の責任追及の動き ―日韓の新たな火種となるか― |
藤谷昌敏 | |
| 自国民救出から産業スパイ、アフリカ支配まで ―仏情報機関の知られざる活動― |
丸谷元人 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第138~139回 報告 | 長野禮子 | |
| 推薦図書 | 推薦図書 |
|
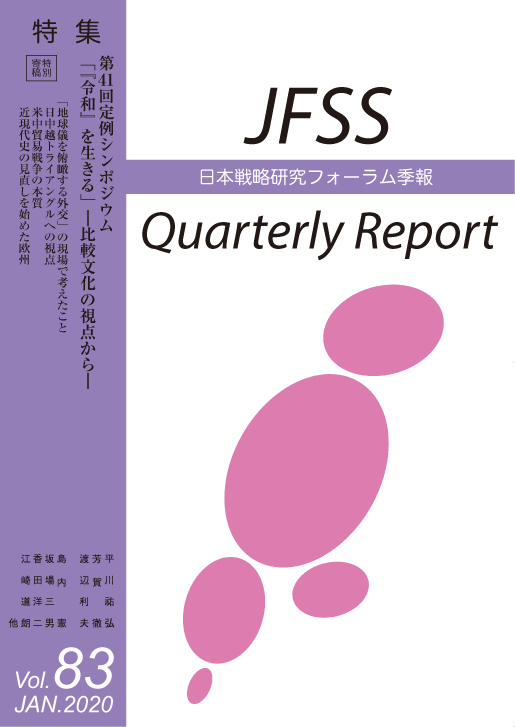
― 目次 ―
| 会長挨拶 | “本論を張れない野党の悲哀 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 柴五郎と日英同盟 ―国際的信頼の重要性― | 丹羽文生 |
| 【特集】第41回 定例シンポジウム報告 「『令和』を生きる」―比較文化の視点から― |
||
| 《講 演》 | 三点測量のすすめ | 平川祐弘 |
| 「令和」におけるエリート再生への期待―幕末武士から近代の指導者たちへと顧みて― | 芳賀 徹 | |
| 改元を機に考える血脈、天皇、そして日本 | 渡辺利夫 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 中国を利する日本の対中戦略 | 屋山太郎 | |
| 「地球儀を俯瞰する外交」の現場で考えたこと ―ようやく緒に就いた日本外交のグローバル化― |
島内 憲 | |
| 日中越トライアングルへの視点 | 坂場三男 | |
| 米中貿易戦争の本質 | 香田洋二 | |
| 日本共産党の二つの厄介事 ―高齢化と中国共産党― | 筆坂秀世 | |
| 日米同盟は機能するのか? | 矢野一樹 | |
| 近現代史の見直しを始めた欧州 | 江崎道朗 | |
| 「ワシントン海軍軍縮条約」の当時から学べる教訓―中華人民共和国の本質を見極めることに向かって | ジェイソン・ モーガン |
|
| (Eng.) | Lessons from the Washington Naval Treaty: Uncovering the True Nature of the People’s Republic of China |
Jason Morgan |
| 「英国のEU 脱退」そんなに驚くべきことではない!? | 副島豊次郎 | |
| 一層の奮起必要の憲法改正―中曽根元首相の「遺言」 ―「中山ルール」の弊害― | 有元隆志 | |
| 【特別研究】 | ||
| 北朝鮮潜水艦発射弾道ミサイルの本当の実力 ―ミサイルの開発は進むが、発射母体である潜水艦の建造は遠い将来になるだろう― | 西村金一 | |
| AI強国を目指す中国の軍事改革―特徴と問題点― | 下平拓哉 | |
| 世界規模のサイバー戦争に備えよ ―進化する北朝鮮のサイバーテロ― |
藤谷昌敏 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第132~137回 報告 | 長野禮子 | |
| 推薦図書 | 推薦図書 | |
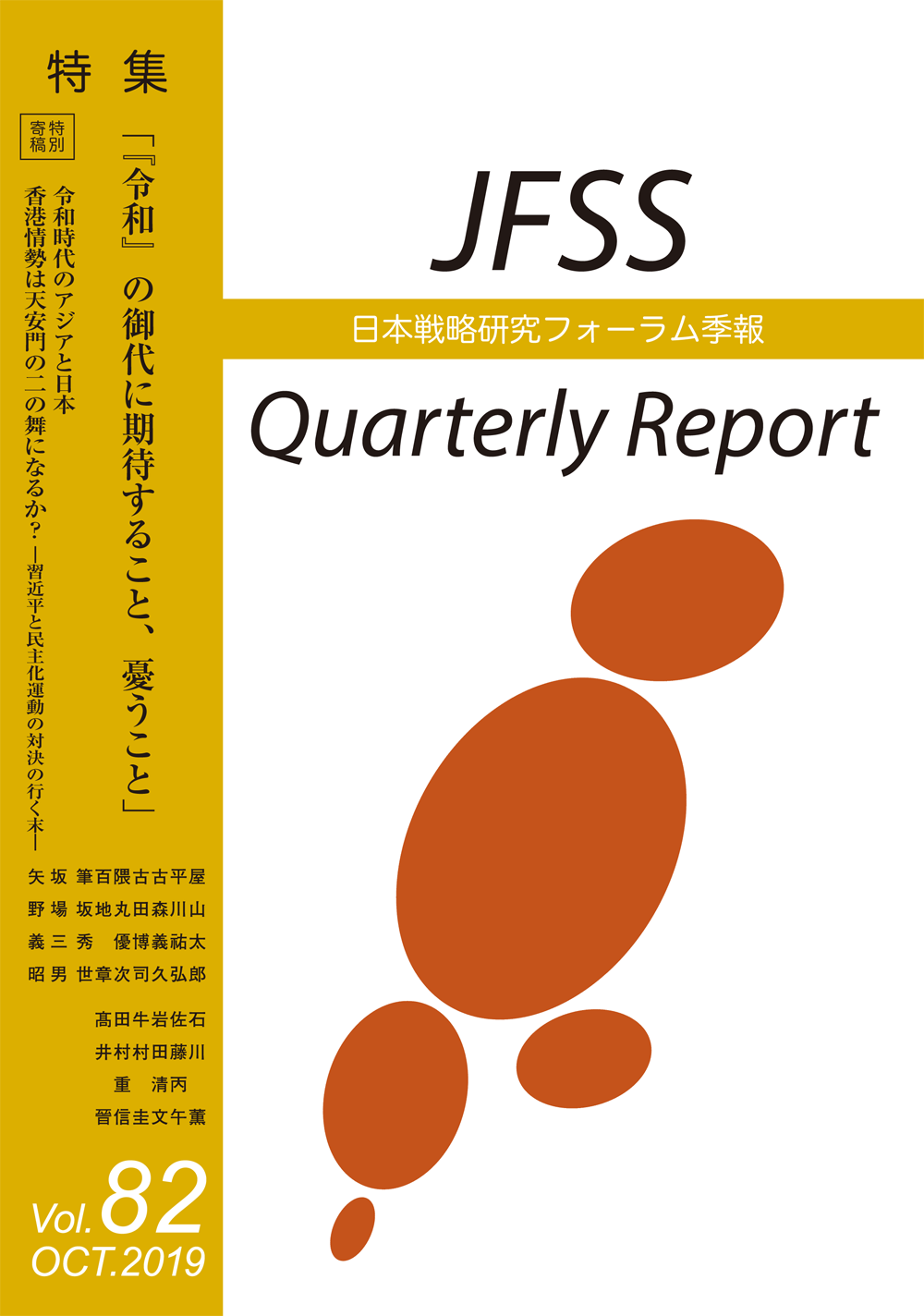
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 改めて「福沢諭吉論」を繙く | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 台湾の歴史教科書における日本統治の評価 | 丹羽文生 |
| 【特集】「『令和』の御代に期待すること、憂うこと」 | ||
| 国際社会の劇的変化に対応せよ | 屋山太郎 | |
| 日本人の世界認識 | 平川祐弘 | |
| 「令和」で成すべきは「憲法改正」 | 古森義久 | |
| 進歩史観の終焉・普遍信仰の崩壊・国家理性の確立 ―平成の御代から令和の御代への政治思想の推移― | 古田博司 | |
| 国際環境の劇的変化に敏感たれ ―「自分の国は自分で守る」覚悟を― | 隈丸優次 | |
| 男系による皇位の安定的継承 | 百地 章 | |
| 令和に入って得意のレトリックも使えなくなった日本共産党 | 筆坂秀世 | |
| 令和という時代に想う | 石川 薫 | |
| 平成時代の国際政治 ―平成の30年を振り返る― | 佐藤丙午 | |
| 「令和」の御代に期待を込めて | 岩田清文 | |
| (Eng.) | (Summary) Expectation toward the Imperial Era Reiwa | Iwata Kiyofumi |
| 令和新時代に歴史意識を考える | 牛村 圭 | |
| 平成の防衛政策の進展と令和の憲法改正 | 田村重信 | |
| 国家間関係におけるルール・オブ・ロー(法の支配) | 髙井 晉 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 令和時代のアジアと日本 | 坂場三男 | |
| 香港情勢は天安門の二の舞になるか? ―習近平と民主化運動の対決の行く末― | 矢野義昭 | |
| 【特別研究】 | ||
| 北朝鮮が最近見せつけた短距離弾道ミサイルと大口径長射程ロケット | 西村金一 | |
| 中国のサイバー戦略と活動 ―サイバー空間で進む軍民融合― | 下平拓哉 | |
| 我が国に対するインテリジェンス活動にどう対応するのか(最終章) | 藤谷昌敏 | |
| 各国の「防衛外交」への取組 ―英仏豪米中の事例調査から― | 西田一平太 | |
| イラン・イラク戦争と日本 ―1987年のペルシャ湾安全航行問題を見直す― | 加藤博章 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第129~131回 報告 | 長野禮子 | |
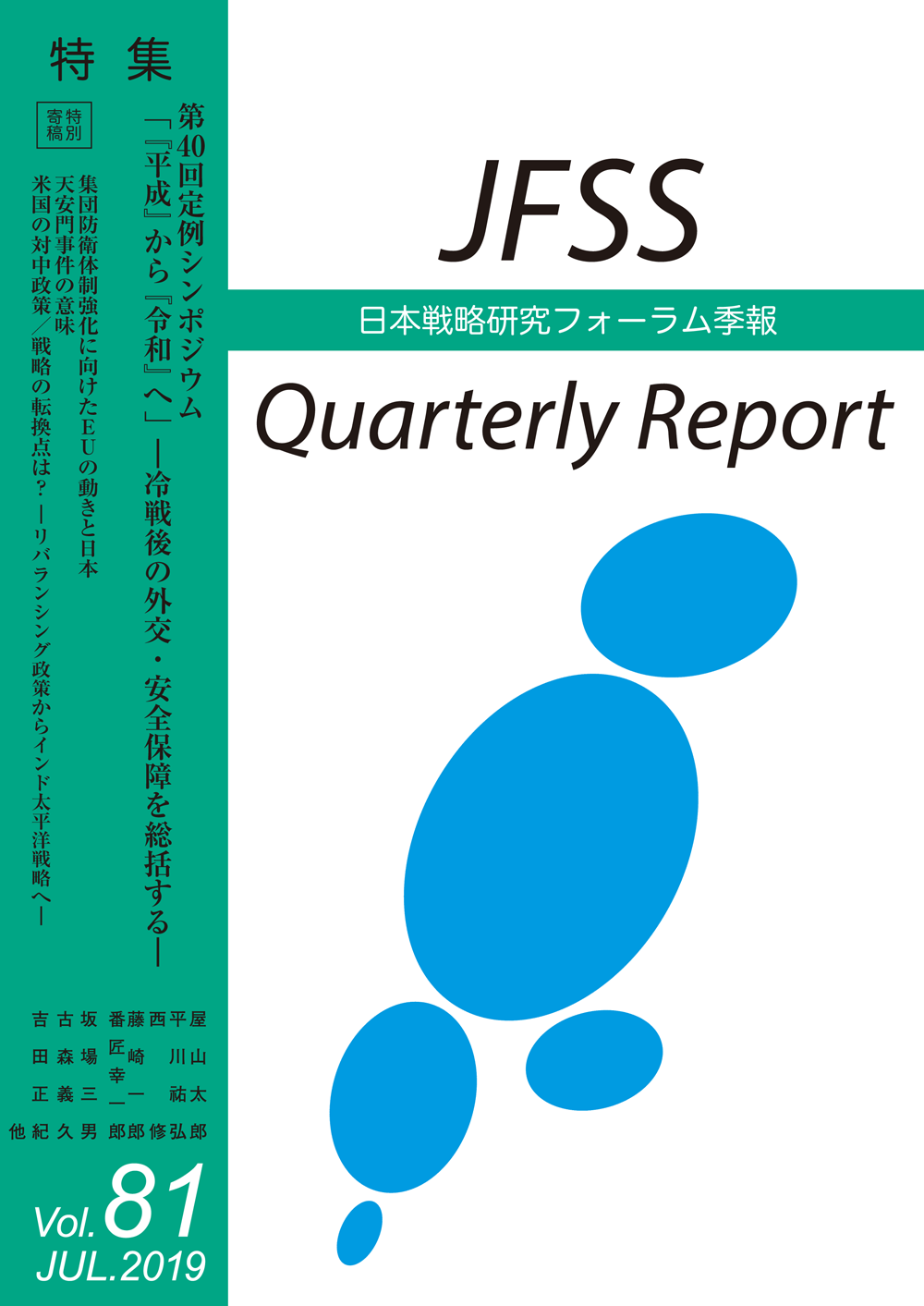
― 目次 ―
| 会長挨拶 | “日本の祭り”に見る日本民族の永い歴史と文化 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | チベット動乱60年 | 丹羽文生 |
| 【特集】第40回 定例シンポジウム報告 「『平成』から『令和』へ」―冷戦後の外交・安全保障を総括する― | ||
| 《報 告》 | 平成30年度外務省補助金事業終了報告 | 佐藤庫八 |
| 内閣府大臣官房政府広報室委託「海外セミナー」終了報告 | 小野田治 | |
| 《プロローグ》 | 平成を総括する | 屋山太郎 |
| 《基調講演》 | 平成に安んずるなかれ | 平川祐弘 |
| 《講 演》 | 憲法論議の課題 | 西 修 |
| 北朝鮮、中国、米国とどう向き合うか | 藤崎一郎 | |
| 平成と自衛隊 ―防人の任務を振り返って― | 番匠幸一郎 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 集団防衛体制強化に向けたEUの動きと日本 | 坂場三男 | |
| 天安門事件の意味 | 古森義久 | |
| 米国の対中政策/戦略の転換点は? ―リバランシング政策からインド太平洋戦略へ― | 吉田正紀 | |
| 日本と台湾に迫り来る中国の脅威 ―チベットとウイグルから学ぶべきこと― | ペマ・ギャルポ | |
| 大成功だったインドの空爆 ―限定的な武力行使の成功例― | 長尾 賢 | |
| (Eng.) | India's Airstrikes Proved Greatly Successful ―Successful Case of Limited Use of Force― | Satoru Nagao |
| 次期台湾総統選挙のゆくえ― | 澁谷 司 | |
| 【特別研究】 | ||
| 北朝鮮による今回の射撃には、中・露軍事衛星システムの支援があった―日本のミサイル防衛は、宇宙と一体化したミサイル攻撃に対応しなければならない― | 西村金一 | |
| 中国の北極政策の核心―中国初の『北極政策白書』を読み解く― | 下平拓哉 | |
| 我が国に対するインテリジェンス活動にどう対応するのか(第4・5章) | 藤谷昌敏 | |
| スリランカ同時多発テロの背景にある米中印の暗闘 | 丸谷元人 | |
| 総合安全保障を考え直す | 加藤博章 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第126~128回 報告 | 長野禮子 | |
| 推薦図書 | 『李氏朝鮮 最後の王 李垠』 | |
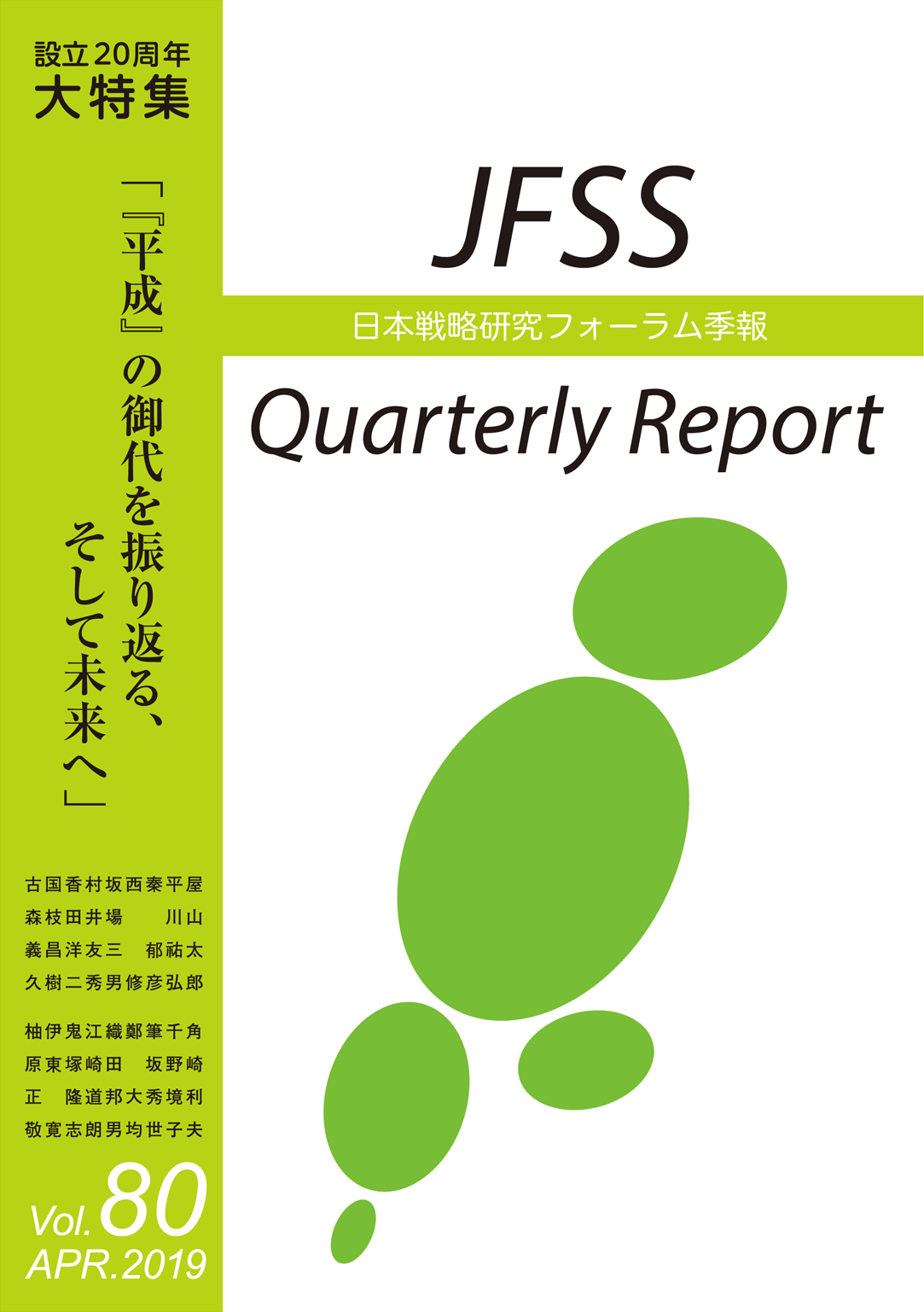
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 元駐日韓国大使の発言に異議あり | 屋山太郎 |
| 副会長挨拶 | 就任のご挨拶にかえて | 佐藤 謙 |
| 巻頭言 | 鄭南榕と「言論の自由の日」 | 丹羽文生 |
| 【特集】「『平成』の御代を振り返る、そして未来へ」 | ||
| 「近年の日本政治を振り返って」 | 屋山太郎 | |
| 平成に安んずるなかれ | 平川祐弘 | |
| 日韓歴史戦の恩怨(おんえん) | 秦 郁彦 | |
| 平成における憲法論議 ―私の体験を踏まえて― | 西 修 | |
| 平成時代の日本外交とこれからの課題 | 坂場三男 | |
| 平成時代の中国脅威論 | 村井友秀 | |
| 軍隊に一歩近づいた自衛隊 ―されど道なお遠く― | 香田洋二 | |
| 私の平成時代の3つの戦争 | 国枝昌樹 | |
| 外からみた平成時代 | 古森義久 | |
| 「平成」を振り返って | 角崎利夫 | |
| ジャーナリストから見た「平成」 | 千野境子 | |
| 平成と日本共産党 | 筆坂秀世 | |
| 平成の日韓関係と新世代の登場 | 鄭 大均 | |
| 安全保障の観点から | 織田邦男 | |
| 皇室を支える国民の務め | 江崎道朗 | |
| 益々強まる他国等の宣伝工作とスパイ活動に対抗する先行的・実際的な施策を確立し実行する必要がある | 鬼塚隆志 | |
| サイバーセキュリティ ―平成の30年― | 伊東 寛 | |
| 日本と台湾の30年 ─東日本大震災をきっかけに新局面を迎えた日台関係― | 柚原正敬 | |
| 【特別研究】 | ||
| 第2回米朝会談 ―金正恩のぬか喜び、その後の失望と屈辱、そしてどう動く― | 西村金一 | |
| 中国の太平洋島嶼地域への関与と日本の対応 | 下平拓哉 | |
| 我が国に対するインテリジェンス活動にどう対応するのか | 藤谷昌敏 | |
| 【講座】 | ||
| 我が国の危機の本質 | 福地 惇 | |
| 【報告】 | ||
| 海外セミナー終了報告 | ||
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第124~125回 報告 | 長野禮子 | |
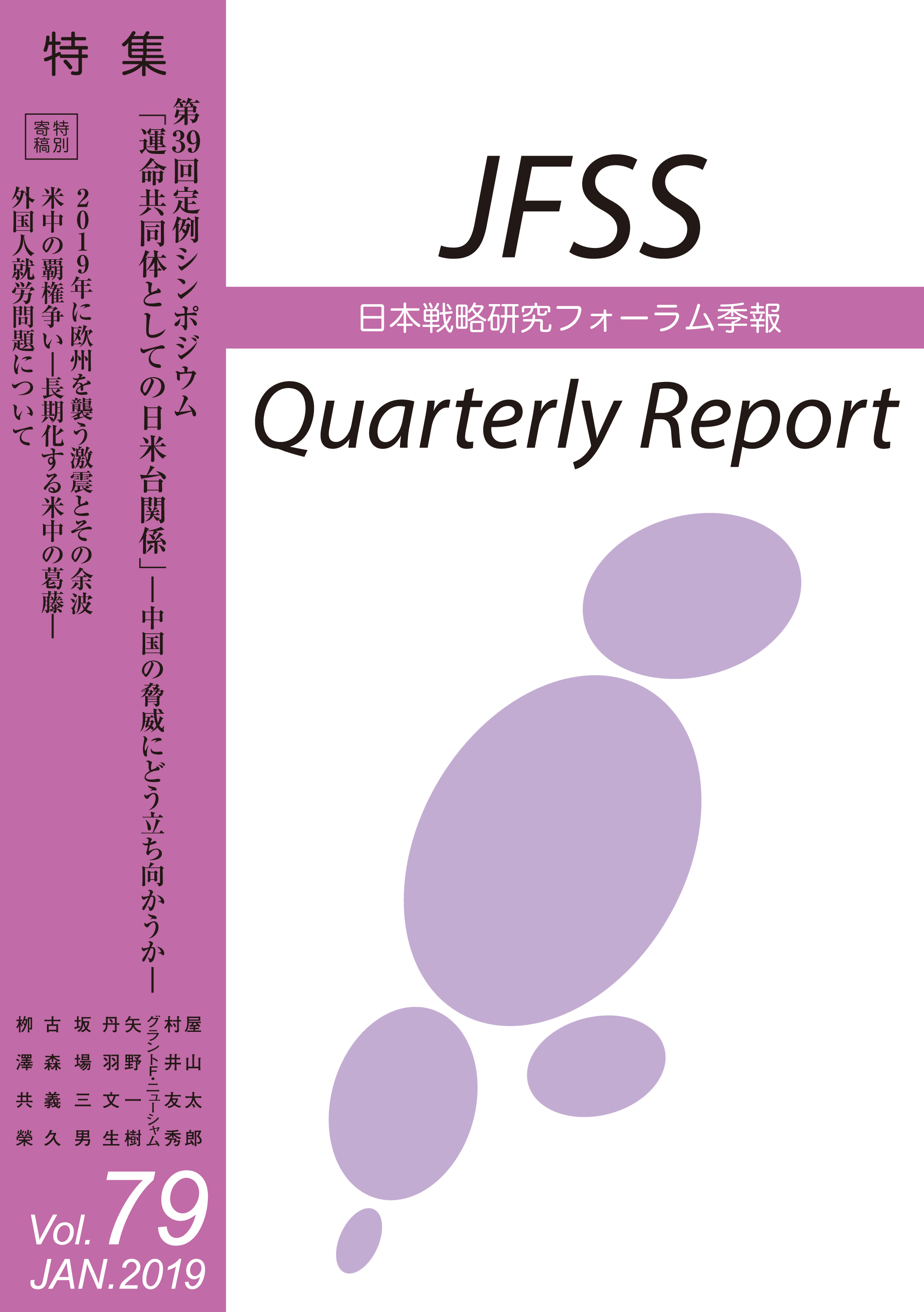
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 自民党に燻る親中派が対中政策を誤る | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | パリ講和会議と日本 | 丹羽文生 |
| 対外発信助成会出版報告 | 秦郁彦著『慰安婦と戦場の性』英訳 | 平川祐弘 |
| 【特集】第39回 定例シンポジウム報告 「運命共同体としての日米台関係」―中国の脅威にどう立ち向かうか― | ||
| 《プロローグ》 | 日米台連携強化のために | 屋山太郎 |
| 《講 演》 | 台湾は日本防衛の生命線 | 村井友秀 |
| アジアの自由を守る―日米台間の協力 | グラント F・ニューシャム | |
| 安全保障面からの日本の台湾支援策について | 矢野一樹 | |
| 日台関係と中国:「72年体制」の再検証 | 丹羽文生 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 2019年に欧州を襲う激震とその余波 | 坂場三男 | |
| 日米中三国関係の行方 | 古森義久 | |
| 米中の覇権争い―長期化する米中の葛藤― | 伊藤俊幸 | |
| 「憲法改正」とその先― 何のための「9条の2」か? | 堂下哲郎 | |
| 米中対決を「新冷戦」と呼ぶのは正しくない | 筆坂秀世 | |
| 外国人就労問題について | 栁澤共榮 | |
| 「軍事技術研究について」―軍事研究をしないと言うだけで、軍事研究をしていないことになるのか?― | 西山淳一 | |
| 【特別研究】 | ||
| 北朝鮮軍によるソウル無血占領の危機が近づいている―南北融和の隠された罠と北による南侵戦略の変化― | 西村金一 | |
| 中国人民解放軍戦略支援部隊の特徴と課題 | 下平拓哉 | |
| 我が国に対するインテリジェンス活動にどう対応するのか | 藤谷昌敏 | |
| 【講座】 | ||
| 歴史認識と日本民族の命運 | 福地 惇 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第118~123回 報告 | 長野禮子 | |
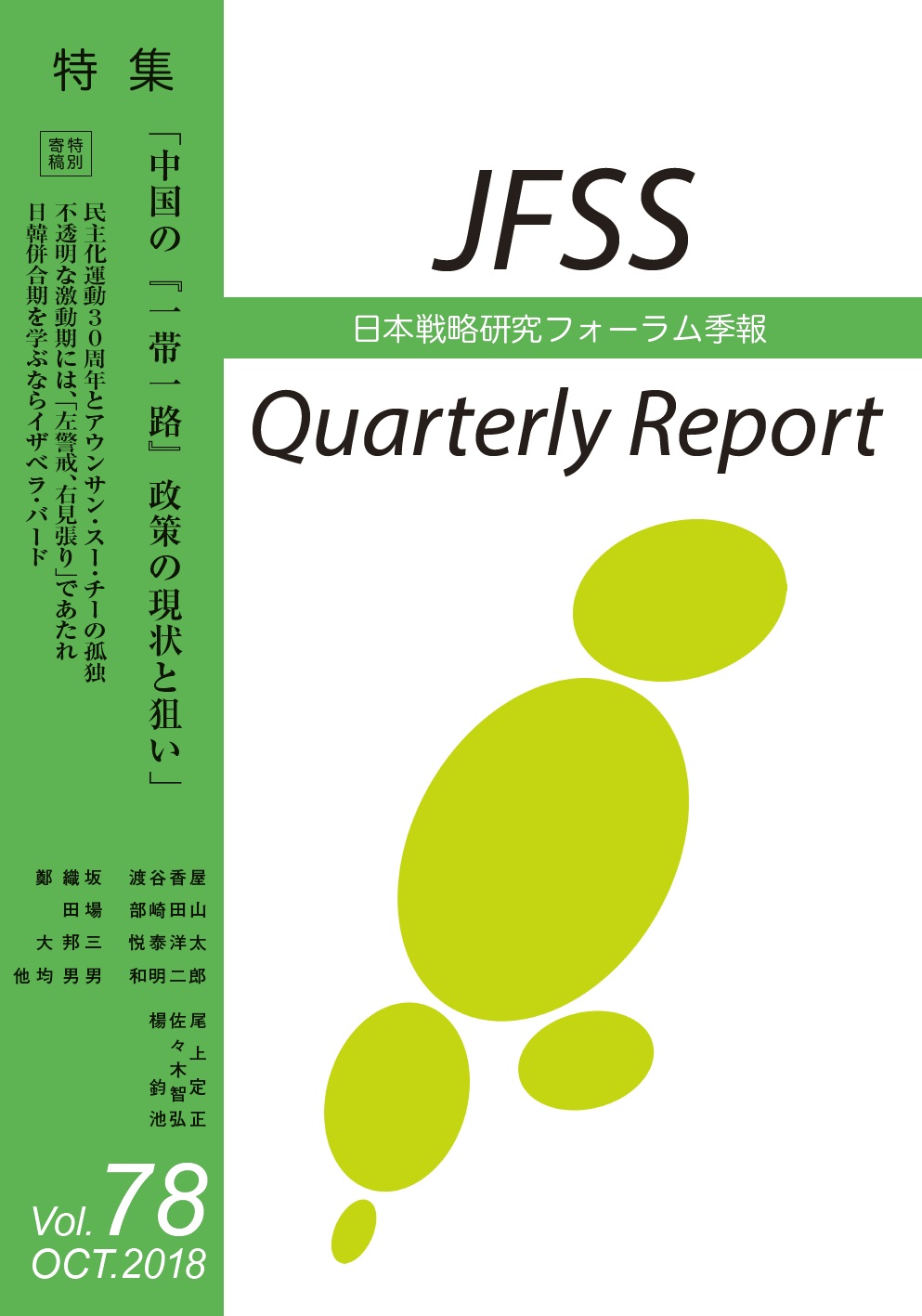
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 安倍晋三首相の国家運営と展望 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 加速する台湾の断交ドミノ ―「中華民国」の鎧を脱ぎ捨てる好機 ― | 丹羽文生 |
| 【特集】「中国の『一帯一路』政策の現状と狙い」 | ||
| 「一帯一路」構想の実態 ―新冷戦時代始まる― | 屋山太郎 | |
| 構想発表から5年:正体が見えてきた一帯一路構想 | 香田洋二 | |
| 一帯一路構想 ―インドネシアの事例― | 谷崎泰明 | |
| 一帯一路構想 ―米中の覇権争いと中国「債務帝国主義」の視点から― | 渡部悦和 | |
| 中国の一帯一路:Digital Silk Road と文明の衝突 | 尾上定正 | |
| 中国の「一帯一路」イニシアティブと新国際秩序構築 | 佐々木智弘 | |
| 中国主導の「一帯一路」がアジア太平洋地域にもたらした衝撃についての分析 | 楊 鈞池 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 民主化運動30周年とアウンサン・スー・チーの孤独 | 坂場三男 | |
| 不透明な激動期には、「左警戒、右見張り」であたれ | 織田邦男 | |
| 日韓併合期を学ぶならイザベラ・バード | 鄭 大均 | |
| 健全な肉体と健全な精神は無関係 | 筆坂秀世 | |
| 56年ぶりの宴のまえに ―ふたたび迎える東京五輪― | 牛村 圭 | |
| 保守が守らねばならないもの | 石川裕一 | |
| 【特別研究】 | ||
| 非核化を進める気がない北朝鮮、米国の仕掛けと日本の備え | 西村金一 | |
| 中国の宇宙計画と特徴 | 下平拓哉 | |
| 我が国に対するインテリジェンス活動にどう対応するのか | 藤谷昌敏 | |
| 【講座】 | ||
| 敗戦国体制の本質を考える(下) | 福地 惇 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第116~117回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
| 英訳本のご紹介・推薦図書 | ||
| 英訳本のご紹介 | ||
| 推薦図書 | ||
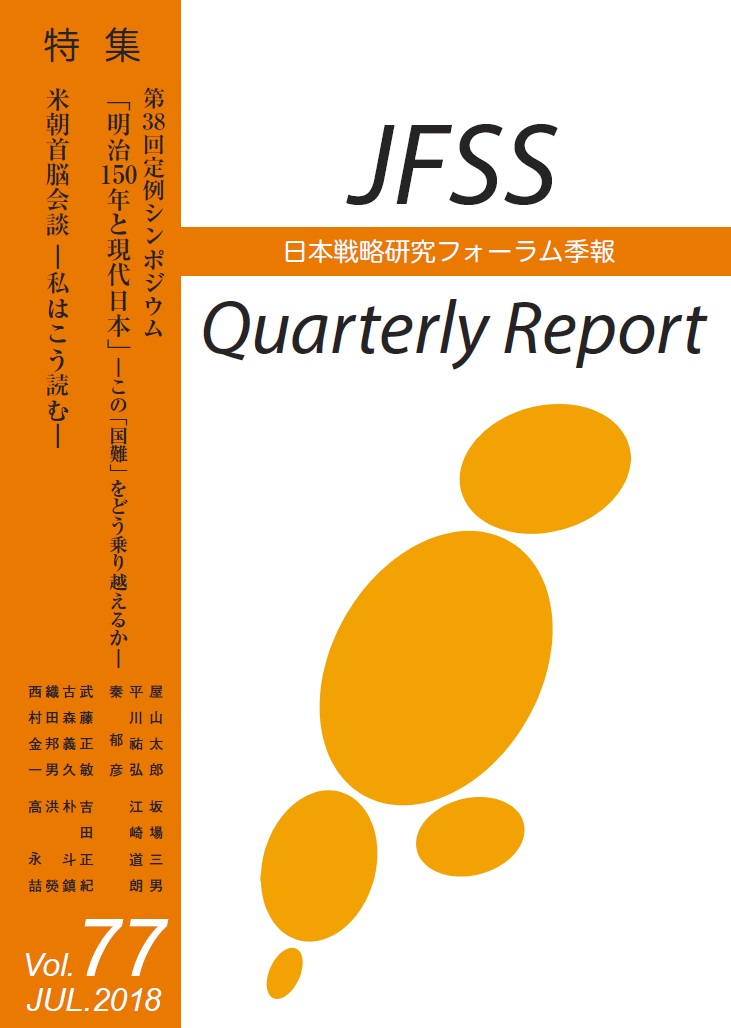
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 東アジア情勢を一変させた米朝首脳会談 ―北朝鮮の中国回帰で始まる米朝交渉の行方― | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 政治家の評価 ―将来を見据えた決断― | 丹羽文生 |
| 【特集Ⅰ】第38回 定例シンポジウム報告 「明治150年と現代日本」―この「国難」をどう乗り越えるか― | ||
| 《プロローグ》 | 海外から見た日本と安倍政権の国家運営 | 屋山太郎 |
| 《基調講演》 | 明治維新はアジア諸国の人に何を意味したか | 平川祐弘 |
| 《講 演》 | 明治150年と靖国神社 | 秦 郁彦 |
| 明治政府と戦後日本 ―「富国強兵」の過去と「富国弱兵」の未来― | 坂場三男 | |
| 思想から見る150年、主として共産主義を中心に | 江崎道朗 | |
| 【特集Ⅱ】米朝首脳会談―私はこう読む― | ||
| 北朝鮮の非核化は実現するのか | 武藤正敏 | |
| 米朝首脳会談の意味するもの | 古森義久 | |
| 米朝首脳会談と今後の展望 ―北朝鮮は核を放棄しない。日本は最悪を想定し準備を― | 織田邦男 | |
| 表舞台に出てきた金正恩の深層にある意図を読む ―北朝鮮には、核・ミサイルを廃棄する意志は見えない。嘘つき国家に変わりない― | 西村金一 | |
| トランプ政権500日と米朝首脳会談 | 吉田正紀 | |
| トランプ敗北、北朝鮮の非核化は実現しない | 朴 斗鎮 | |
| 米朝首脳会談と東アジアの現状変更 | 洪 熒 | |
| 米朝首脳会談の裏面合意と今後の見通し ―肯定的な側面と否定的な側面― | 高 永喆 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| インドの超大国化を阻む3つの「闇」 | 坂場三男 | |
| 共産党との距離感に悩む野党の現状 | 筆坂秀世 | |
| 【特別研究】 | ||
| 中国海軍造船力の実態と展望 | 下平拓哉 | |
| フランスから見た最近のテロ動向 ―ISの中東領土支配は終焉へ、欧州でのテロリスクは依然として残る― | 吉田彩子 | |
| 【講座】 | ||
| 敗戦国体質の本質を考える(中) | 福地 惇 | |
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||
| 第115回 報告 | 長野禮子 | |
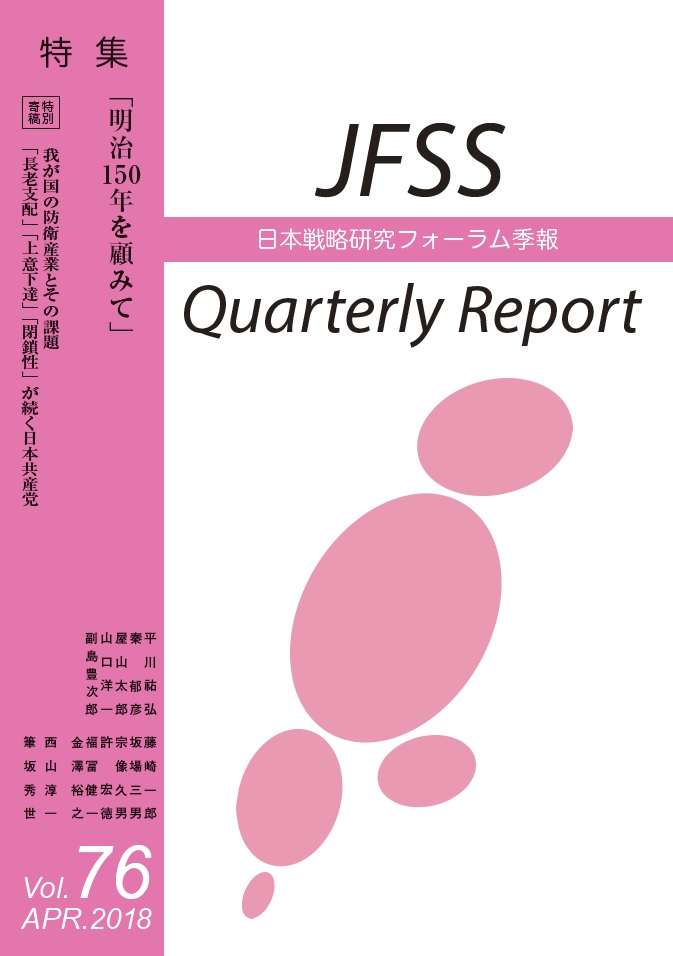
― 目次 ―
| 会長挨拶 | トランプ大統領の対中国・北朝鮮戦略 ―日米両首脳の共通認識と日米豪印の戦略的連携― | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 秋山兄弟と日露戦争 ―「御国の為め」に― | 丹羽文生 |
| 【特集】「明治150年を顧みて」 | ||
| 明治維新はアジア諸国の人に何を意味したか | 平川祐弘 | |
| 明治150年ところどころ ―幻の「百年計画」― | 秦 郁彦 | |
| 明治維新150年に想う | 屋山太郎 | |
| 地上の楽園ここにあり | 山口洋一 | |
| スロバキアの歴史問題 | 副島豊次郎 | |
| 「大常識」で思う明治150年 | 藤崎一郎 | |
| 海の向こうから見た「明治維新」 | 坂場三男 | |
| 明治150年 ―世界と日本の「動き」に“横串”を入れると違った「歴史」が見える― | 宗像久男 | |
| 明治日本と台湾の近代化 | 許 宏德 | |
| 日本の近代と伊藤博文の「知のフォーラム」構想 ―共産主義を肯定した吉田ドクトリンの「知の断絶」とその克服― | 福冨健一 | |
| 幕末日本の海軍建設 | 金澤裕之 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 我が国の防衛産業とその課題 | 西山淳一 | |
| 「長老支配」「上意下達」「閉鎖性」が続く日本共産党 | 筆坂秀世 | |
| 【特別研究】 | ||
| 北朝鮮の苦悩が見える軍創建70周年記念日と平昌オリンピック | 西村金一 | |
| 中国海軍の能力と活動 | 下平拓哉 | |
| 【講座】 | ||
| 敗戦国体制の本質を考える(上) | 福地 惇 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第112~114回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
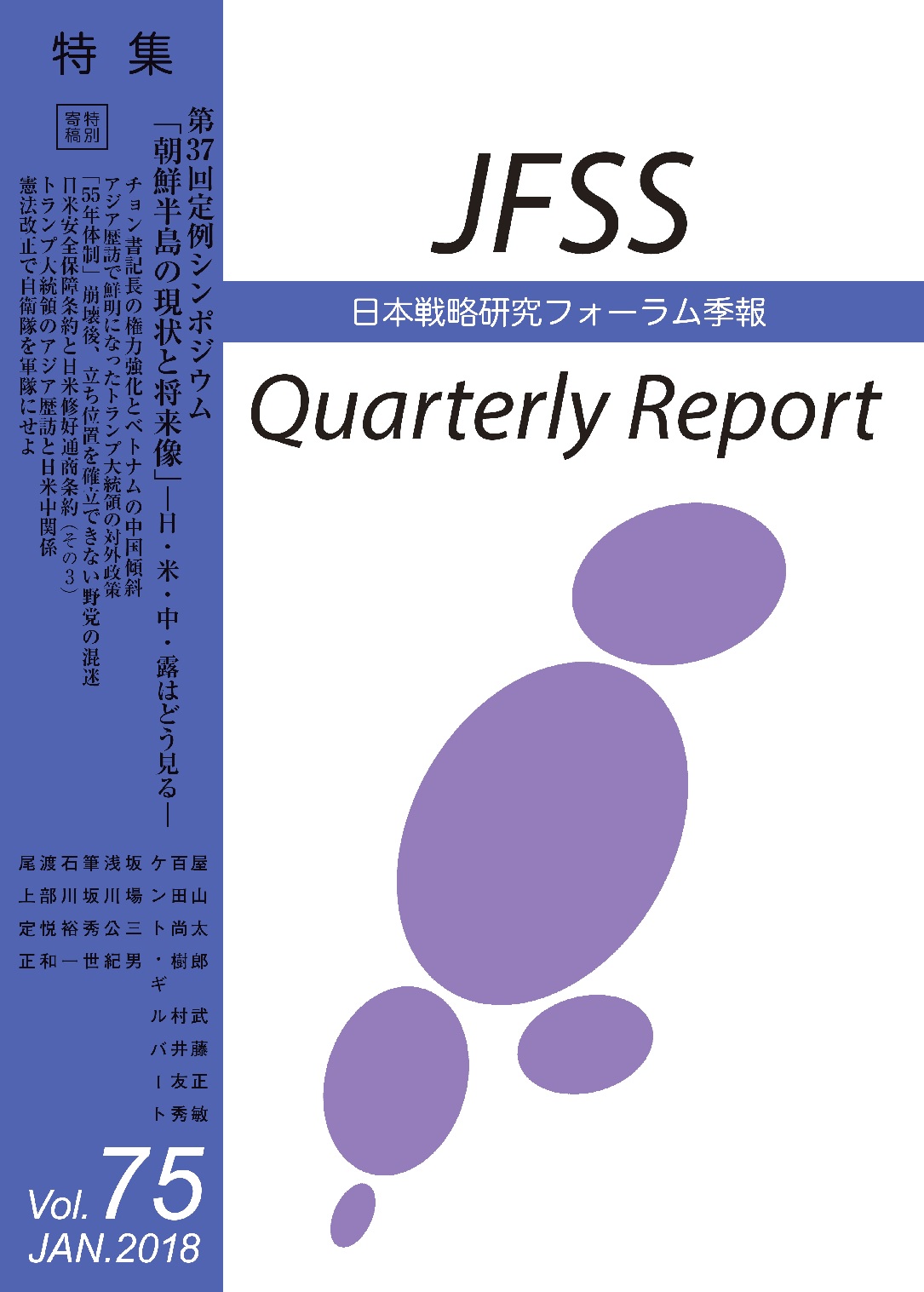
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 新年を寿ぎ、安倍政権に期待する | 屋山太郎 | ||||||
| 巻頭言 | バシー海峡に散華した英霊を偲ぶ | 丹羽文生 | ||||||
| ||||||||
| 《報 告》 | 北朝鮮を変える | 武藤正敏 | ||||||
| 今こそ韓国に謝ろう | 百田尚樹 | |||||||
| 中朝関係の実像 | 村井友秀 | |||||||
| 儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 | ケント・ギルバート | |||||||
| 《オープンディスカッション》 | ||||||||
| (上記4氏によるディスカッション) | ||||||||
| 【特別寄稿】 | ||||||||
| チョン書記長の権力強化とベトナムの中国傾斜 | 坂場三男 | |||||||
| アジア歴訪で鮮明になったトランプ大統領の対外政策 | 浅川公紀 | |||||||
| 「55年体制」崩壊後、立ち位置を確立できない野党の混迷 | 筆坂秀世 | |||||||
| 日米安全保障条約と日米修好通商条約(その3) | 石川裕一 | |||||||
| トランプ大統領のアジア歴訪と日米中関係 | 渡部悦和 | |||||||
| 憲法改正で自衛隊を軍隊にせよ | 尾上定正 | |||||||
| 【特別研究】 | ||||||||
| 侮れなくなった北朝鮮のサイバー戦能力 | 西村金一 | |||||||
| 北朝鮮との「同化」を目指す韓国・文在寅政権 朝鮮戦争再開時、韓国軍は参戦するのか? | 野口裕之 | |||||||
| 「作戦術」とは何か | 下平拓哉 | |||||||
| 【講座】 | ||||||||
| シナ大陸の泥沼戦争に日本軍を誘導したのは何者だ! | 福地 惇 | |||||||
| 【Key Note Chat 坂町】 | ||||||||
| 第107回~第111回 報告 | 長野禮子 | |||||||
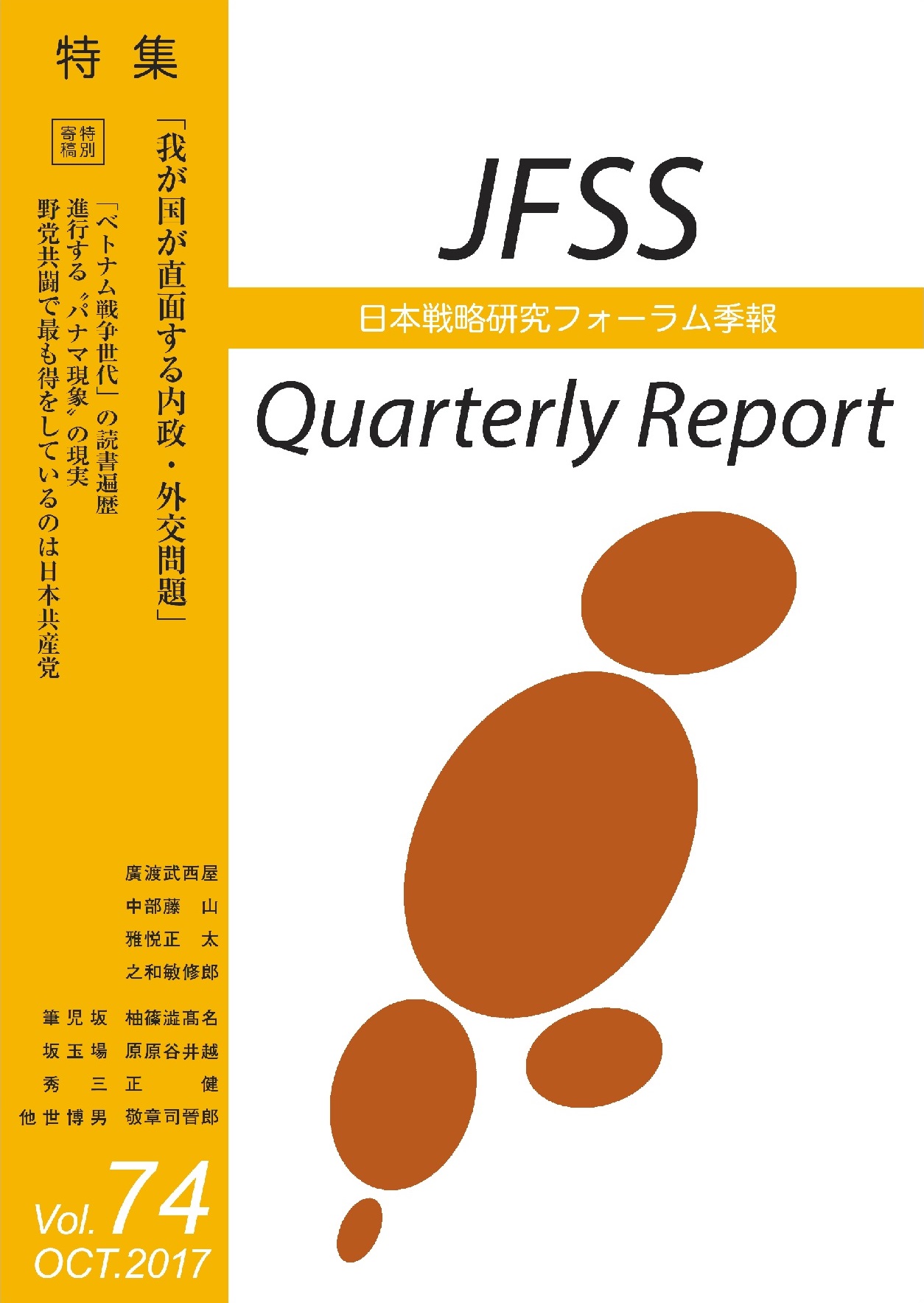
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 日英同盟を彷彿させたメイ首相の来日 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 明治150年を迎えるに当たって | 丹羽文生 |
| 【特集】「我が国が直面する内政・外交問題」 | ||
| 戦後73年、大きく揺らぐ世界秩序 ―外交・安全保障政策と日本の自立― | 屋山太郎 | |
| 憲法第9条の発案者は幣原首相かマッカーサー元帥か | 西 修 | |
| 朝鮮半島との関係は日本外交にとって最大の試練 ―核・ミサイルを放棄しない北朝鮮とどう向き合うのか?文在寅政権下の日韓関係は今後一層難しくなる― | 武藤正敏 | |
| 国家の最高指導者に必要な資質 ―内政と外交の観点から― | 渡部悦和 | |
| ワシントン D.C.で米国の国家安全保障政策・戦略について考える | 廣中雅之 | |
| 安倍外交に転機、戦略修正も | 名越健郎 | |
| 忍び寄る中国の尖閣諸島奪取への対処 | 髙井 晉 | |
| 中国「19大」の人事 | 澁谷 司 | |
| 日韓関係の「歪み」を正す奥茂治氏の闘い ―出国禁止・韓国からの報告― | 篠原 章 | |
| 深化する日台関係の課題 | 柚原正敬 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 「ベトナム戦争世代」の読書遍歴 | 坂場三男 | |
| 進行する“パナマ現象”の現実 | 児玉 博 | |
| 野党共闘で最も得をしているのは日本共産党 | 筆坂秀世 | |
| 日米安全保障条約と日米修好通商条約(その2) | 石川裕一 | |
| 印中関係とアジアの平和 | ペマ・ギャルポ | |
| 【特別研究】 | ||
| 北朝鮮の弾道ミサイル解説 | 西村金一 | |
| 中国海警局の特徴と日本の対応 | 下平拓哉 | |
| 【講座】 | ||
| 東亜の大戦乱に太平洋問題調査会が果たした役割について | 福地 惇 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第102~106回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
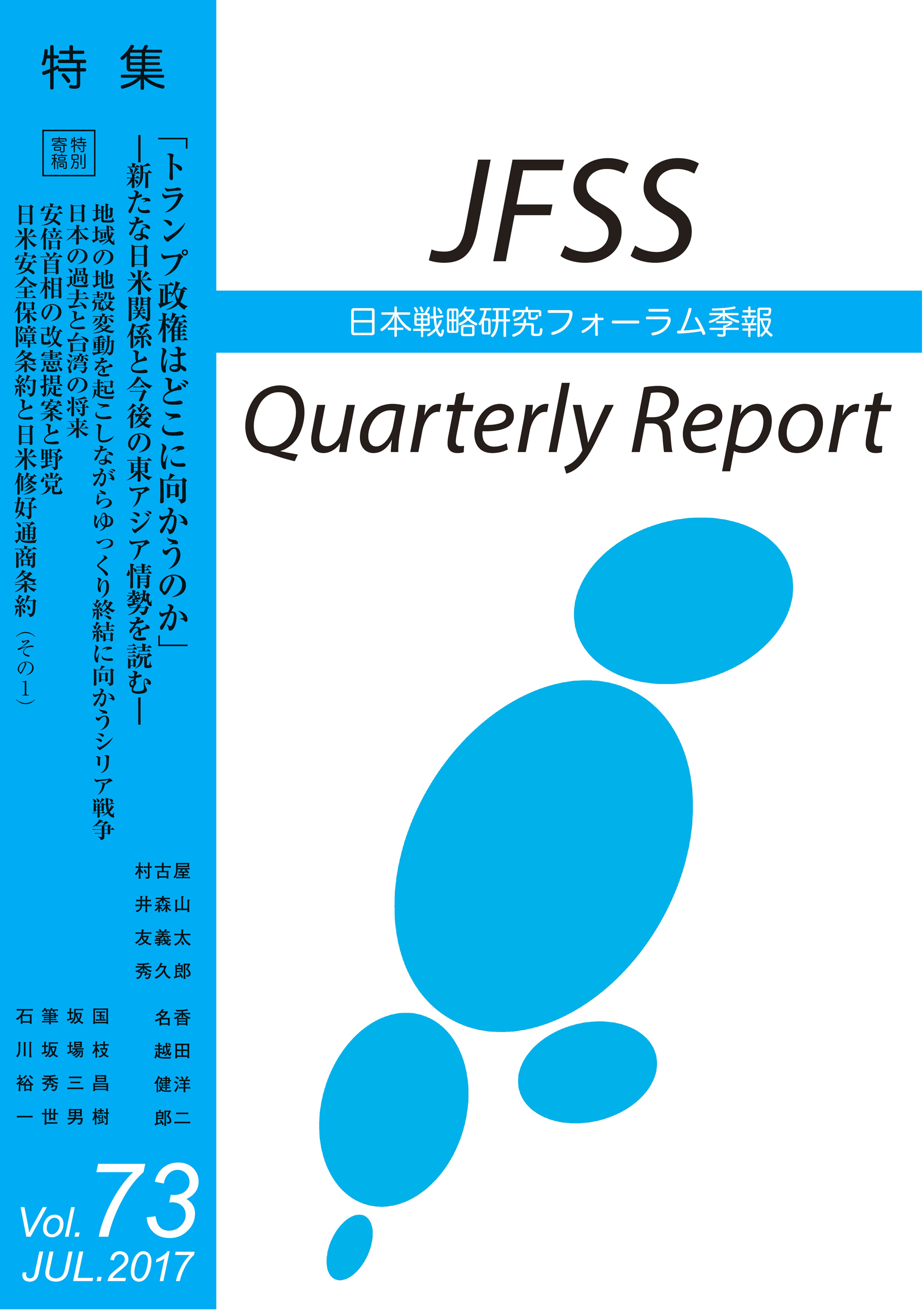
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 米・中、2超大国が国際社会に与える影響 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 溶解する民進党 | 丹羽文生 |
| 【特集】第36回 定例シンポジウム報告 「トランプ政権はどこに向かうのか」 ―新たな日米関係と今後の東アジア情勢を読む― | ||
| 《基調講演》 | 世界が直面している3つの混沌と安倍政治 | 屋山太郎 |
| 《報 告》 | トランプ政権の読み方の陥穽 | 古森義久 |
| 中国共産党の行動原理と戦略 | 村井友秀 | |
| トランプ政権誕生の背景と東アジア政策 | 香田洋二 | |
| トランプ登場後の米露・日露関係 | 名越健郎 | |
| 《オープンディスカッション》 | ||
| (上記4氏によるディスカッション) | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| 地域の地殻変動を起こしながら ゆっくり終結に向かうシリア戦争 | 国枝昌樹 | |
| 日本の過去と台湾の将来 | 坂場三男 | |
| 安倍首相の改憲提案と野党 | 筆坂秀世 | |
| 日米安全保障条約と日米修好通商条約(その1) | 石川裕一 | |
| 【特別研究】 | ||
| ロシアが北朝鮮の軍事技術 (特に、弾道ミサイル)開発を支えている | 西村金一 | |
| 中国海上民兵の実態と日本の対応 ―海南省の実例を中心に― | 下平拓哉 | |
| 【講座】 | ||
| 西安事件について | 福地 惇 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第98回~第101回 報告 | 長野禮子 | |
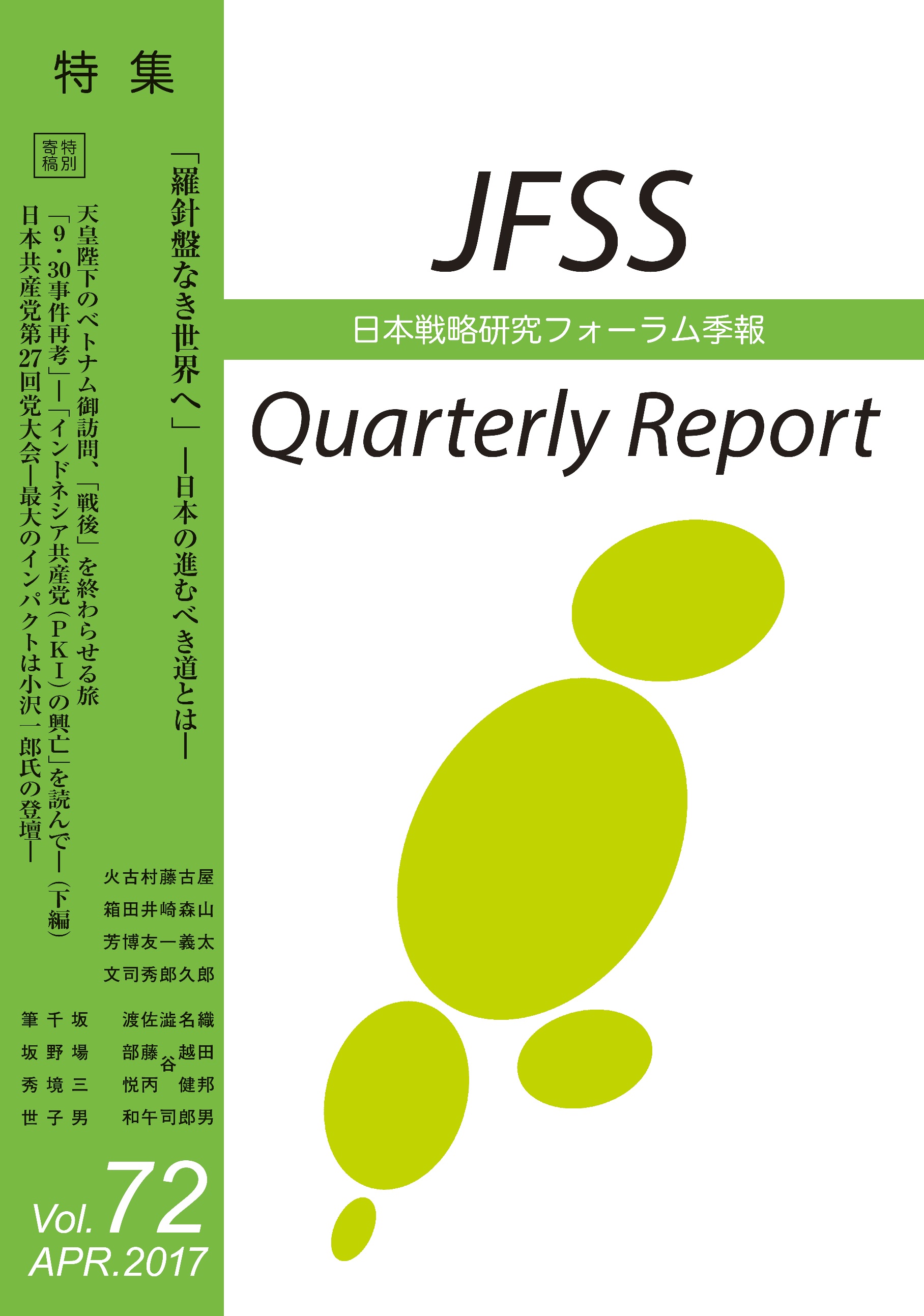
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 行動で浮かび上がるトランプ氏の人物像 | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | ―身独立して―国独立す | 丹羽文生 |
| 【特集】「羅針盤なき世界へ」―日本の進むべき道とは― |
||
| 資本主義は“実験”結果を教訓として育っていく | 屋山太郎 | |
| 新しい時代に対応できる国家へ | 古森義久 | |
| ぶれても揺らがぬトランプさん | 藤崎一郎 | |
| 中国の海洋進出と対抗戦略 | 村井友秀 | |
| 日本は韓国・北朝鮮に関し冷酷なる羅針盤をもって歩め | 古田博司 | |
| トランプ政権と日米同盟 | 火箱芳文 | |
| 日米首脳会談後の「次の一手」を考える | 織田邦男 | |
| 対露外交をどう立て直すか | 名越建郎 | |
| 安倍政権の対中政策 | 澁谷 司 | |
| 「リベラル国際主義」の動揺と日本の将来 | 佐藤丙午 | |
| アナーキーな世界においても日本は王道を歩め | 渡部悦和 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 天皇陛下のベトナム御訪問、「戦後」を終わらせる旅 | 坂場三男 | |
|
「9・30 事件再考」 ―「インドネシア共産党(PKI)の興亡」を読んで―(下編) |
千野境子 | |
|
日本共産党第27回党大会 ―最大のインパクトは小沢一郎氏の登壇― |
筆坂秀世 | |
| 【特別研究】 | ||
|
金正恩委員長は南侵の決断を躊躇しない ―南北の軍事衝突から日本人の命を守る対策を考察する― |
西村金一 | |
|
日本の防衛力強化と役割の拡大 ―専守防衛にまず必要なもの― |
下平拓哉 | |
| 【講座】 | ||
|
「日米和解」は如何にあるべきか ―戦争挑発者は誰だったか― |
福地 惇 | |
| 【Key Note Chat坂町】 | ||
| 第94~97回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
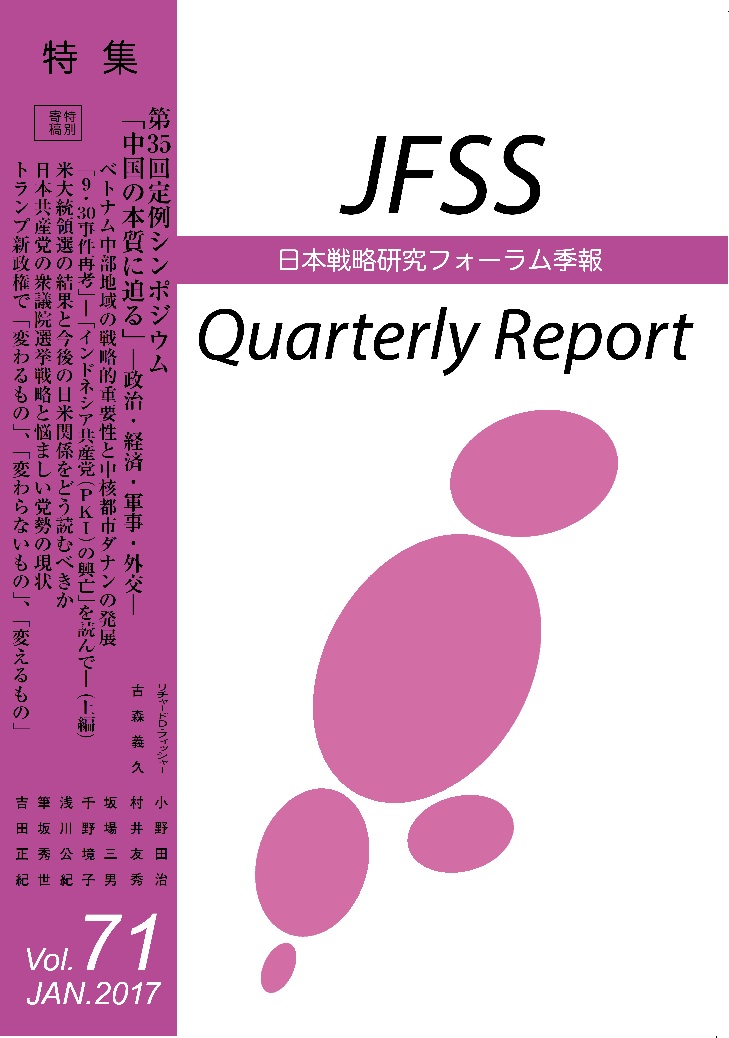
― 目次 ―
| 新春を迎えて | 天皇は続くことに意味がある | 平川祐弘 |
| 会長挨拶 | 政治の安定が国民の安寧をもたらす | 屋山太郎 |
| 巻頭言 | 吉田政治「負の遺産」 | 丹羽文生 |
| 【特集】第35回 定例シンポジウム報告 「中国の本質に迫る」―政治・経済・軍事・外交― | ||
| 中国の地域的、地球的及び宇宙的な兵力の投入 | リチャード・フィッシャー | |
| (Eng.) | China's Path To Regional,Global and Space Power Projection | Richard D.Fisher Jr. |
| 中国の「反日」構造を探る | 古森義久 | |
| 中国の三戦(世論戦・心理戦・法律戦) ―米国防省ネットアセスメント室の資料から― | 小野田治 | |
| 中国共産党の行動原理 | 村井友秀 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| ベトナム中部地域の戦略的重要性と中核都市ダナンの発展 | 坂場三男 | |
| 「9・30 事件再考」 ―「インドネシア共産党(PKI)の興亡」を読んで―(上編) | 千野境子 | |
| 米大統領選の結果と今後の日米関係をどう読むべきか | 浅川公紀 | |
| 日本共産党の衆議院選挙戦略と悩ましい党勢の現状 | 筆坂秀世 | |
| トランプ新政権で「変わるもの」、「変わらないもの」、「変えるもの」 | 吉田正紀 | |
| 【特別研究】 | ||
| 2016 年夏の北朝鮮ミサイル発射は、中国との連携プレーだ ―その背景にある中国の軍事戦略― | 西村金一 | |
| 日本の防衛 ―海洋安全保障からの3 つの視点― | 下平拓哉 | |
| ≪講座≫ | ||
| 「欺瞞の歴史」を克服して國體の復権を目指そう | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第90回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
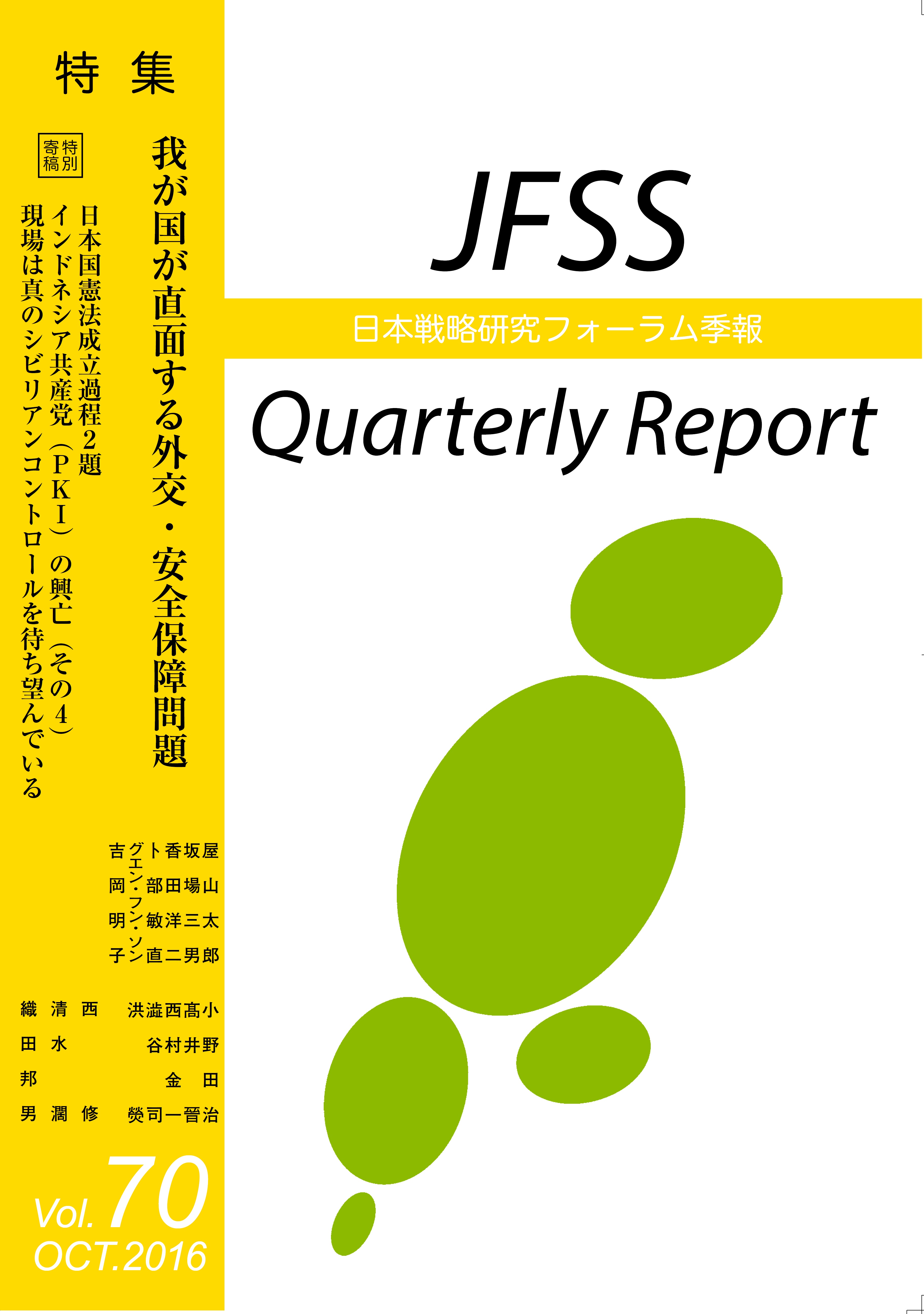
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 我が国を取り巻く外交・安全保障環境 | 平林 博 |
| 巻頭言 | 松陰の攘夷論とグローバリズム | 丹羽文生 |
| 【特集】我が国が直面する外交・安全保障問題 | ||
| 日本外交の基本は古来「対中国」 | 屋山太郎 | |
| 英国のEU離脱と欧州統合の課題 | 坂場三男 | |
| 中国の南シナ海人工島造成と日本の安全保障 | 香田洋二 | |
| 南シナ海問題をフィリピンから見て―王様は裸― | 卜部敏直 | |
| ベトナムと南シナ海の仲裁裁判所判決 | グエン・フン・ソン | |
| (Eng.) | Vietnam and the South China Sea's Arbitral Tribunal Rulings | Nguyen Hung Son |
| 極東開発協力は領土問題解決の橋頭堡になるか | ||
| ―安倍首相、対露「8項目提案」の焦点― | 吉岡明子 | |
| | 新たな時代を迎えた日米安全保障協力 中国の南シナ海進出に対する仲裁裁判所の裁定 著しく変化してきている北朝鮮の軍事的脅威 蔡英文政権発足後の台湾と最近の香港情勢 避けられない韓半島の現状変更 | 小野田治 髙井 晉 西村金一 澁谷 司 洪 熒 |
| 【特別寄稿】 | ||
| 日本国憲法成立過程2題 | 西 修 | |
| インドネシア共産党(PKI)の興亡 | ||
| ―9.30事件の顚末―(その4) 現場は真のシビリアンコントロールを待ち望んでいる | 清水 濶 織田邦男 | |
| 【特別研究】 | ||
| 高高度電磁パルス(HEMP)攻撃の対応準備を急げ | 鬼塚隆志 | |
| 日米同盟の深化と海上自衛隊 ―協調と拒否による創造的関与戦略― | 下平拓哉 | |
| フランスから見る欧州・中東・アフリカ情勢(その3) テロの脅威が続くヨーロッパ ―フランスで起きた神父殺害事件から― | 吉田彩子 | |
| ≪講座≫ | ||
| 「欺瞞の歴史」について | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat 坂町≫ | ||
| 第86回~89回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
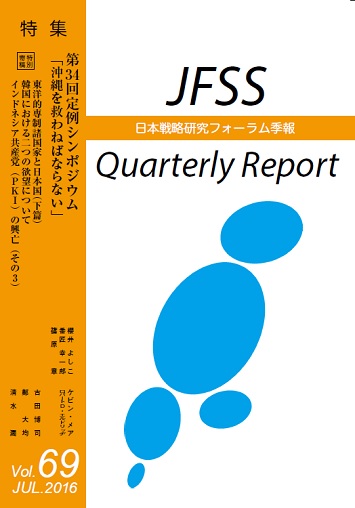
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 歴史を画した伊勢志摩サミットとオバマ大統領の広島訪問 | 平林 博 |
| 巻頭言 | 沖縄で起きた許し難い犯行 | 丹羽文生 |
| 【特集】第34回定例シンポジウム報告「沖縄を救わねばならない」 | ||
| 《基調講演》 | ウチナンチュウとヤマトンチュウ、共に手を携えて | 櫻井よしこ |
| 《報 告》 | 沖縄「基地問題」の背景 | ケビン・メア |
| 沖縄の戦略的重要性と南西防衛態勢 | 番匠幸一郎 | |
| 「沖縄問題」の解決に向けて | ロバートD.エルドリッジ | |
| データで見る『沖縄の不都合な真実』 | 篠原 章 | |
| 《オープンディスカッション》 | ||
| (上記4氏によるディスカッション) | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| 東洋的専制諸国家と日本国(下篇) | 古田博司 | |
| 韓国における二つの欲望について | 鄭 大均 | |
| (Eng.) | On the Two Desires in South Korea | Chung Daekyun |
| (韓国語) | 한국의 ' 두 가지 욕망 ' 에 대해서 | 정대균 |
| インドネシア共産党(PKI)の興亡(その3) | 清水 濶 | |
| 【特別研究】 | ||
| 2016年米国大統領選挙とアジア太平洋の安全保障 | 下平拓哉 | |
| フランスから見る欧州・中東・アフリカ情勢(2) | 吉田彩子 | |
| ≪講座≫ | ||
| 「歴史戦」の本当の意味 | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第85回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
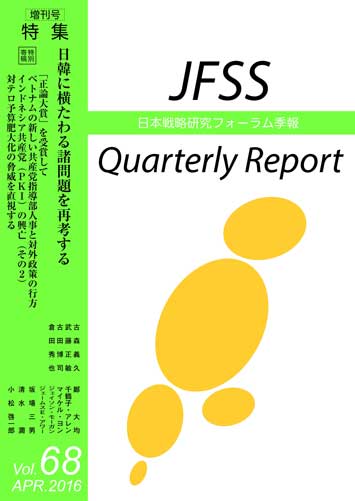
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 慰安婦問題の日韓合意は生き続けるか | 平林 博 |
| 巻頭言 | 修学旅行の適地-人気上昇中の台湾- | 丹羽文生 |
| 【特集】日韓に横たわる諸問題を再考する | ||
| いま慰安婦とアメリカ | 古森義久 | |
| (Eng.) | America and the Comfort Women Today | |
| 韓国は日本や米国との関係を見直そうとしている | 武藤正敏 | |
| 東洋的専制諸国家と日本国(上篇) | 古田博司 | |
| 冷戦終結後の日韓関係と「進歩主義」の挑戦 | 倉田秀也 | |
| 日本人が韓国に伝えるべきこと | 鄭 大均 | |
| 慰安婦問題の本質と支配・被支配の枠組み | 千鶴子・アレン | |
| (Eng.) | The Paradigm that Supports the Korean Comfort Women Redress Movement | |
| 単なる教科書問題ではない:継続する「歴史戦」の本質 | マイケル・ヨン、 ジェイソン・モーガン | |
| (Eng.) | Not a Textbook Case : The True Nature of the Ongoing History Wars | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 「正論大賞」を受賞して | ジェームス E.アワー | |
| ベトナムの新しい共産党指導部人事と対外政策の行方 | 坂場三男 | |
| インドネシア共産党(PKI)の興亡 (その 2) | 清水 濶 | |
| 対テロ予算肥大化の脅威を直視する | 小松啓一郎 | |
| 【特別研究】 | ||
| ランド研究所との戦略対話と誤報「ランド研究所の図上演習:日本敗北シナリオ」について | 川村純彦 | |
| ミャンマーの戦略的重要性と日本のアプローチ(3) | 下平拓哉 | |
| フランスから見る欧州・中東・アフリカ情勢(1) テロ脅威と移民難民問題を抱える欧州諸国 | 吉田彩子 | |
| ≪講座≫ | ||
| 「常識の歴史像」の正体を知ろう | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第81~84回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
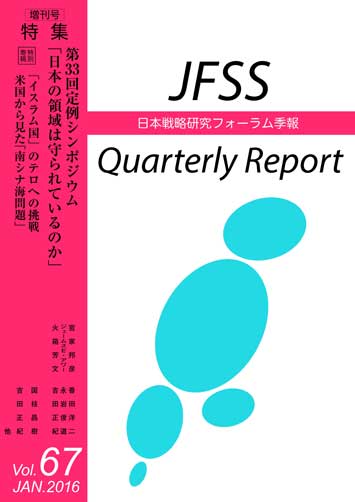
― 目次 ―
| 会長挨拶 | より輝く日本のために | 平林 博 |
| 巻頭言 | 「普通の国」へ前進 | 丹羽文生 |
| 【特集】第33回定例シンポジウム報告「日本の領域は守られているのか」 | ||
| 《基調講演》 | 地政学的分析のススメ | 宮家邦彦 |
| 日本の領域防衛 | 香田洋二 | |
| 《報 告》 | 南シナ海と航行の自由について | ジェームス E.アワー |
| 日本の「空の領域」は守られているか | 永岩俊道 | |
| 我が国を取り巻く安全保障環境の認識と課題 | 火箱芳文 | |
| 「領海を守る」とは? | 吉田正紀 | |
| 《オープンディスカッション》 | ||
| (上記4氏によるディスカッション) | ||
| 【特別寄稿】 | ||
| インドネシア共産党(PKI)の興亡 | 清水 濶 | |
| 「イスラム国」のテロへの挑戦 | 国枝昌樹 | |
| 安全保障政策を考える | 小松啓一郎 | |
| 米国から見た「南シナ海問題」 | 吉田正紀 | |
| インドからの手紙(その4) モディ政権下におけるインドの「アクト・イースト」政策 | ルーパク・ボラ | |
| 【特別研究】 | ||
| ミャンマーの戦略的重要性と日本のアプローチ(2) | 下平拓哉 | |
| パリ同時多発テロとロシア軍機撃墜事件の「闇」 | 丸谷元人 | |
| ≪講座≫ | ||
| 帝国主義列国に翻弄された日本帝国(下) | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第80回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
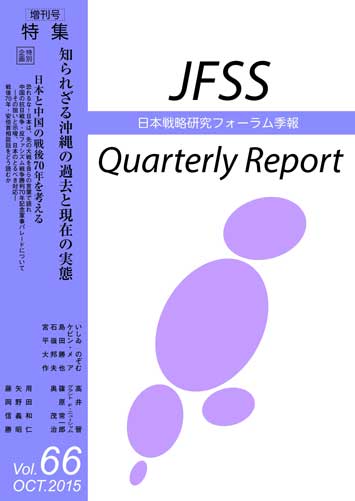
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 徒労に終わった抗日戦争「勝利」70年記念行事 | 平林 博 |
| 巻頭言 | 「現行憲法の自主的改正」未だ成らず | 丹羽文生 |
| 【特集】知られざる沖縄の過去と現在の実態 | ||
| 琉球王朝はなぜ中華思想にゆさぶられたのか | いしゐのぞむ | |
| 在沖縄米軍構成員の法的地位と犯罪の防止 | 髙井 晉 | |
| 沖縄の地政学的重要性と辺野古移設問題 | ケビン・メア | |
| 沖縄の米軍基地 | グラント F.ニューシャム | |
| 日本初の海底電信敷設船「沖縄丸」の軌跡 | 島田勝也 | |
| 日本共産党と沖縄 | 篠原常一郎 | |
| おきなわの世替わりと自衛隊 | 石嶺邦夫 | |
| 集団自決軍命令の虚構を暴く | 奥 茂治 | |
| 沖縄の若者と常識人は辺野古基地を期待する | 宮平大作 | |
| 【特別企画】日本と中国の戦後70年を考える | ||
| 恐れるな!日本は、先の大戦を自らの言葉で語れ | 用田和仁 | |
| 中国の抗日戦争・反ファシズム戦争勝利70年記念軍事パレードについて | 矢野義昭 | |
| 戦後70年・安倍首相談話をどう読むか | 藤岡信勝 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| 1970年代初期のインドネシアに在勤して | 清水 濶 | |
| 生物兵器の実態―その知られざる重要性― | 小松啓一郎 | |
| インドからの手紙(その3) 急速に接近する印日米関係 | ルーパク・ボラ | |
| 【特別研究】 | ||
| ミャンマーの戦略的重要性と日本のアプローチ | 下平拓哉 | |
| 国際法からみた南沙群島における人工島建設 | 髙井 晉 | |
| フランスからのインテリジェンスレポート(その7) フランスから見るヨーロッパの不法移民・難民問題 | 吉田彩子 | |
| ≪講座≫ | ||
| 帝国主義列国に翻弄された日本帝国(上) | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第78回~79回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
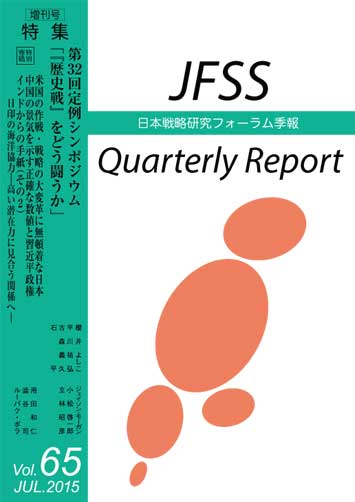
― 目次 ―
| 会長挨拶 | 安倍首脳外交に期待する | 平林 博 |
| 巻頭言 | 戦後70年と「安倍談話」 | 丹羽文生 |
| 【特集】第 32 回定例シンポジウム報告「『歴史戦』をどう闘うか」 | ||
| 《ビデオメッセージ》 | ||
| 「日本の沈黙、いま打ち破るとき」 | 櫻井よしこ | |
| 《基調講演》 | ||
| 悪魔でさえも描かれるほど黒くはない | 平川祐弘 | |
| 「アメリカでの歴史戦」概要 | 古森義久 | |
| 中国が仕掛けた「歴史戦」に日本はどう対処するか | 石 平 | |
| ナチス・ドイツと日本帝国は同類か -東京裁判史観が変更する所以- | ジェイソン・モーガン | |
| 「リビジョニスト」批判の背景にある欧米の心理 | 小松啓一郎 | |
| 米国・中国・韓国の歴史認識を糾すには | 立林昭彦 | |
| 《オープンディスカッション》 | ||
| (上記6氏によるディスカッション) | ||
| 【特別寄】 | ||
| 米国の作戦・戦略の大変革に無頓着な日本 | 用田和仁 | |
| 中国の景気を示す正確な数値と習近平政権 | 澁谷 司 | |
| インドからの手紙(その2) 日印の海洋協力-高い潜在力に見合う関係へ- | ルーパク・ボラ | |
| 【特別研究】 | ||
| フランスからのインテリジェンスレポート(その6) グローバルテロリズム:弱まりを見せないダーイッシュ | 吉田彩子 | |
| ≪講座≫ | ||
| 敗戦後70周年を目前にしての絶望 | 福地 惇 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第76回~77回 報告と雑感 | 長野禮子 | |
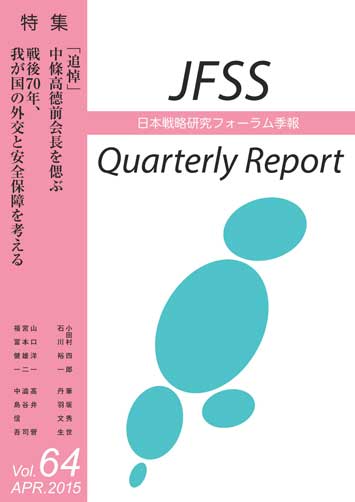
― 目次 ―
| ご挨拶 | 会長代行のご挨拶 | 平林 博 |
| 【追悼】中條高德前会長を偲ぶ | ||
| 前会長中條高德氏のご逝去を悼む | 小田村四郎 | |
| 憂国の思いを引き継いでいきたい | 筆坂秀世 | |
| わが師、中條さんとの思い出 | 石川裕一 | |
| 鬱勃たる憂国の情 | 丹羽文生 | |
| 【特集】戦後70年、我が国の外交と安全保障を考える | ||
| 日本外交戦後70年の軌跡 | 山口洋一 | |
| 外交の55年体制 | 宮本雄二 | |
| 吉田茂、重光葵、岸信介と憲法改正 | 福冨健一 | |
| 日本と国連の70年 | 髙井 晉 | |
| 戦後70年の日華・日中関係 | 澁谷 司 | |
| 指導者達の選択と構想 | 中島信吾 | |
| 【特別寄稿】 | ||
| インドからの手紙(その1) -日本とインド:絆を強めるとき- | ルーパク・ボラ | |
| 「イスラム国」(ISIL)への対応 | 渡部悦和 | |
| 【特別研究】 | ||
| 冷戦後の米国の大戦略とオフショア・バランシングをめぐる議論 | 関根大助 | |
| フランスからのインテリジェンスレポート(その5) 若者達を惹き付けるイスラム過激派 | 吉田彩子 | |
| ≪講座≫ | ||
| シナ事変への道(下) | 福地 惇 | |
| ≪連載≫台湾で愛される日本人(8) | ||
| 台湾で祀られる「トルコの恩人」 | 丹羽文生 | |
| ≪Key Note Chat坂町≫ | ||
| 第72回~75回 報告と雑感 | 長野禮子 | |